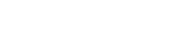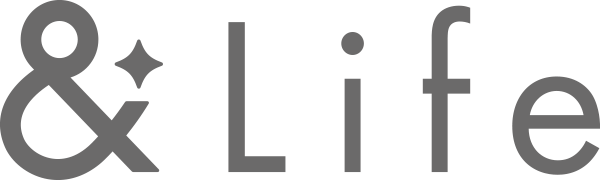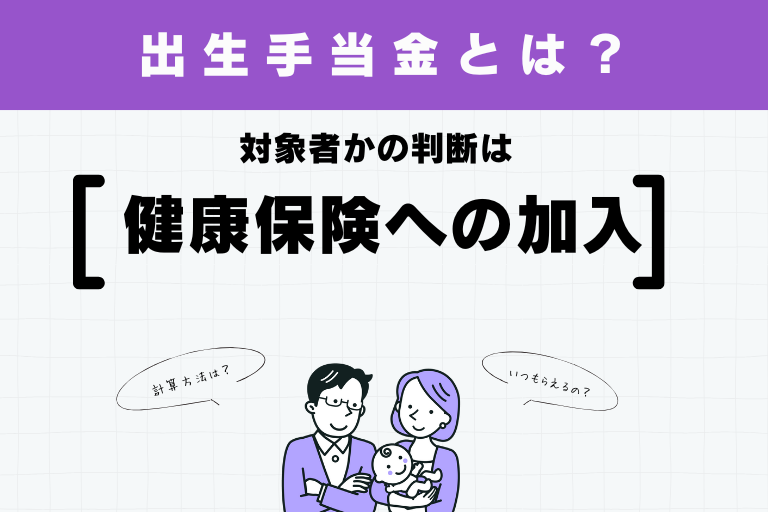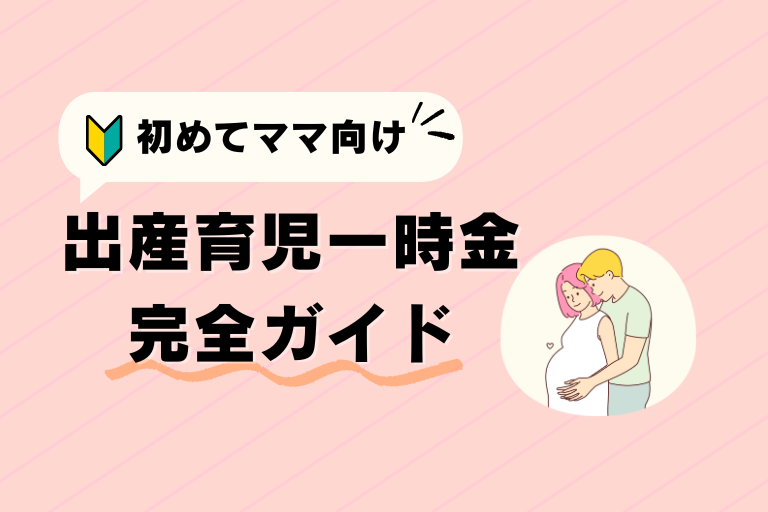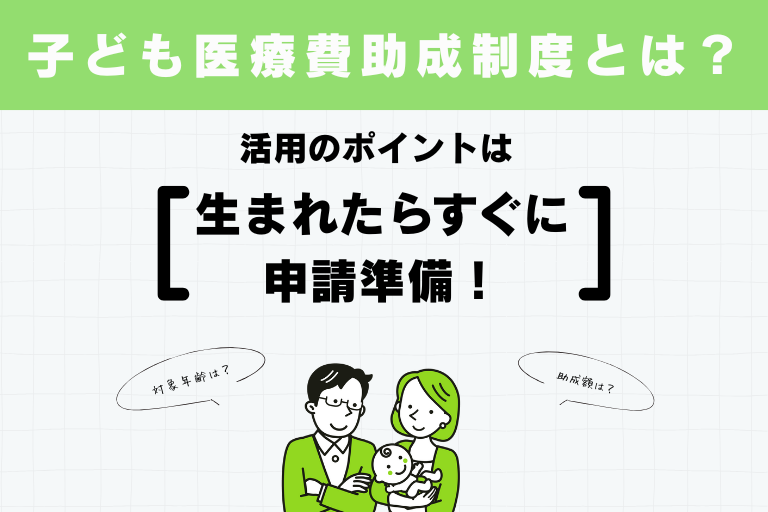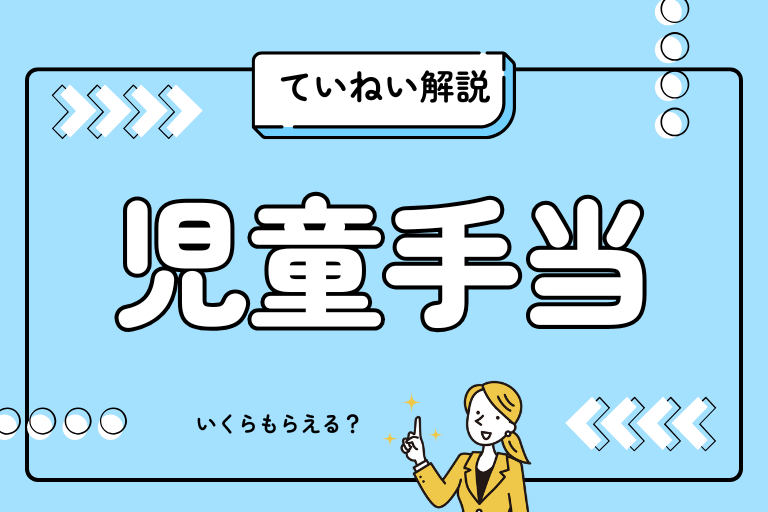『出産育児一時金』と『出産手当金』、どちらも聞くけどその違いって分かりますか?名前が似ていて混乱しやすいこの制度。この記事では、二つの制度の違いを説明し、「出産手当金」についての給付目的や申請方法をわかりやすく解説します。出産育児一時金については、別記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
目次
出産手当金とは?
出産手当金は、会社からの産前・産後の休業中に収入が支給されない場合や減少した場合に女性を経済的にサポートするために健康保険から支給される給付金です。
労働基準法第65条では、妊娠・出産する女性労働者を対象に産前休業と産後休業に関する規定を定めています。妊娠や産後の体力回復を促進し、健康を守るための休業制度を保障するものです。この制度により、女性は体調を優先して安心して休業を取得でき、産前・産後の最適な環境作りが可能となります。
産前休業(労働基準法第65条第1項)
- 期間:出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から取得可能。
- 対象者:妊娠中の女性労働者が「休業を請求」した場合。
- 内容:妊娠中の女性が休業を希望した場合、使用者(雇用主)は就業させてはならない。
※産前休業の期間は出産予定日を基準に計算されます。もし、出産が予定日より遅れた場合でも、予定日から出産日までの期間も「産前休業」として扱われます。
産後休業(労働基準法第65条第2項)
- 期間:産後8週間。ただし、産後6週間経過後に以下の条件を満たせば就業が可能。
女性本人が請求した場合に産後6週間以降に働く意思を示す。
医師が業務に支障がないと認めた場合。 - 対象者:女性労働者が出産のために休業している場合。
- 内容:産後の女性を産後8週間が経過する前に就業させてはならない。ただし、産後6週間を過ぎた後、女性労働者が働きたいと希望し、医師が健康状態に問題ないと判断した場合、一部業務に従事することは認められます。
上記が、労働基準法第65条で定められている休業期間になります。しかし、この法律には給与の支払いの義務は課せられておらず、会社の就業規則によって給与規定が異なるため無給となる場合もあります。このような場合に出産手当金は、経済的負担を軽減する制度として重要です。
また、会社員のほか、雇用形態がパートやアルバイトでも健康保険に加入していれば受給対象となります。ただし、自営業やフリーランスなど、国民健康保険に加入している方は対象外となるため注意しましょう。
出産手当金と出産育児一時金との違い
出産手当金は、産休期間中の生活費補助が目的であるのに対し、出産育児一時金は出産そのものにかかる費用を軽減するための制度です。主な違いは表で確認してみましょう。
| 種別 | 出産手当金 | 出産育児一時金 |
|---|---|---|
| 目的 | 産休中の収入補助 | 出産費用の負担軽減 |
| 対象者 | 健康保険加入している被保険者本人(雇用形態問わず) | 公的医療保険(健保・国保)に加入するすべての方。※扶養者も含む |
| 給付額 | 標準報酬日額の2/3×休業日数 | 一人につき最大50万円(例:双子なら100万円) |
| 対象期間 | 産前・産後の休業期間 | 出産時(妊娠4か月以上) |
| 支給時期 | 申請書の提出から1~2か月後 | 主に医療機関へ直接支払うため定め無し(※支払い方法により異なる) |
大きな違いは、給付額です。出産手当金は、働いていた際の給料がベースで算出されますが、出産育児一時金は一律で1人50万円と定められています。出産手当金の計算方法は、次章で例を交えて詳しく解説します。
>出産育児一時金についての解説はこちらから
出産手当金の計算方法
出産手当金の給付額は以下のように計算されます。
標準報酬日額の2/3が基本
標準報酬日額とは、給付開始日以前の12か月間に支払われた給与総額を30日で割った金額です。
例えば、月給が30万円の場合、給与合計額360万円。
360万円÷12か月÷30日=1万円
標準報酬日額は10,000円。
10,000円×2/3=6,666.6
その2/3である「約6,667円」が1日あたりの給付額となります。
休業日数分支給
出産手当金は、産前42日+産後56日の計98日間が対象。
上記の例では、6,667円×98日=約65万3,366円が給付されることになります。
産休に入ってからの生活費も心配事の1つ。どれくらい支給されるのか、自分の1年間の給与と合わせて確認しましょう。
対象者と申請方法
対象者
出産手当金の対象者となる条件は以下の通りです。
- 勤務先の健康保険に加入している女性
- 妊娠・出産により仕事を休んでいること
- 産休前後の給与が支給されていない、または減額されていること
申請方法
手続きは比較的簡単で、以下の流れで進めます。
- 申請書を用意
まず、勤務先や健康保険組合から「健康保険出産手当金支給申請書」を入手します。不明な項目がある場合は、会社の担当者へ問い合わせしましょう。
- 医療機関からの証明
医師または助産師による証明欄を記入してもらいます。
- 勤務先に提出
勤務先に証明書類を提出し、給与の支給状況を記入してもらいます。勤務先の会社から健康保険組合に申請してもらうことで、最終的に健康保険組合へ申請書を送付します。
【注意点】
申請期間は産休開始から2年以上が期限となっている場合が多いので、余裕をもって提出しましょう。
複雑な場合は勤務先の人事担当者へ事前相談をするとスムーズです。
【休業期間についての特記事項】
出産手当金は休業期間中でも、「あくまで給与が支払われない期間」に限って給付されます。例えば、産前休暇の一部期間に給与が支払われている場合、その期間を除いて計算されます。また、産後休暇が延長される場合も、健康保険組合に連絡することで追加給付が受けられる可能性があります。
まとめ
出産手当金は、産前・産後の休業中に収入が減少する女性に向けた経済的支援制度です。育休中の生活費補助として、標準報酬日額の2/3×休業日数分が給付されるため、家計を支えてくれるはずですよ。申請手続きや条件をしっかり確認して、制度を最大限活用しましょう。
妊娠や出産は人生の大イベント。正しい知識を持つことで不安を軽減し、家計管理を安心して進めることができます。この記事を参考に、出産準備を自信を持って進めてくださいね!
本記事は2025年7月時点の情報です。最新の情報や詳細については、厚生労働省のウェブサイトや、お住まいの自治体の窓口などでご確認ください。