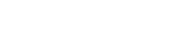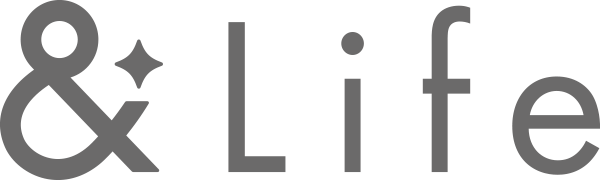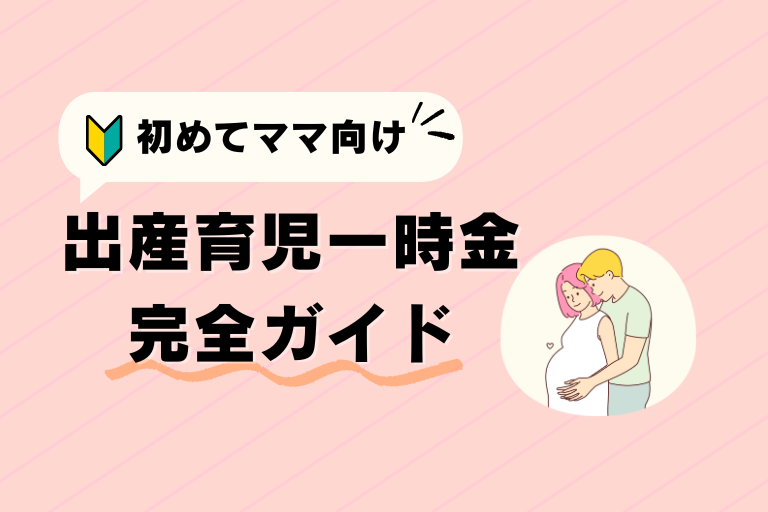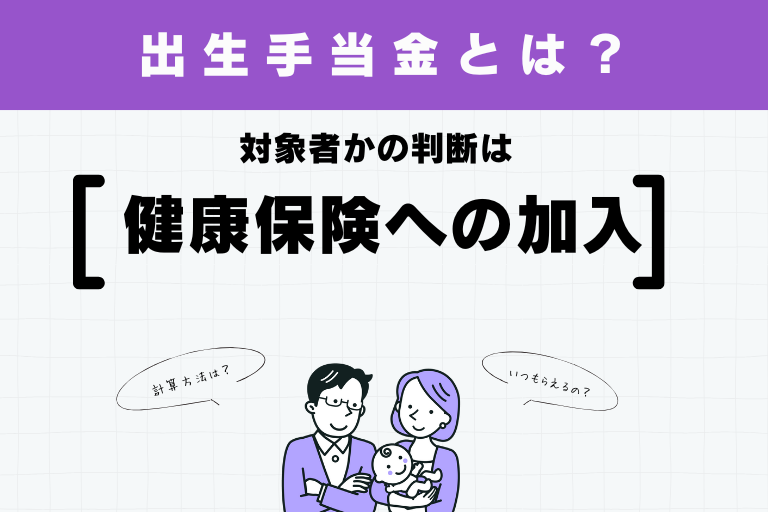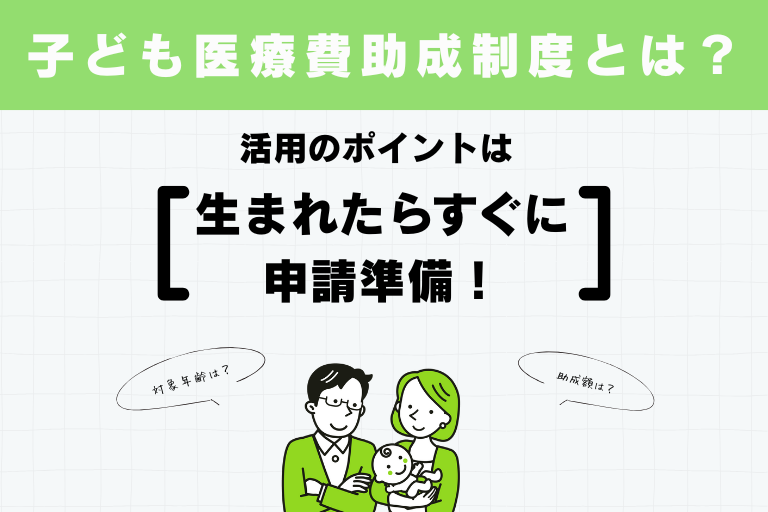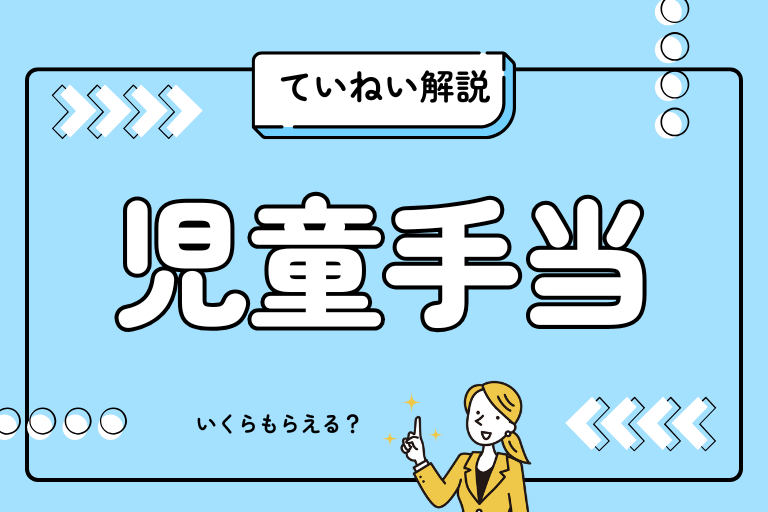「出産育児一時金ってよく聞くけど、具体的に何をしてくれる制度なの?」そんな疑問を持つママも多いはず。この制度は、出産費用を国がサポートしてくれるありがたい仕組み。支払方式によっては簡単に手続きすることができ、煩雑な手続きを減らすこともできます。この記事では、申請や支給までの流れなど、わかりやすく丁寧に解説していきます!
出産育児一時金とは?
「出産育児一時金」は、出産にかかる費用を軽減するために支給される補助金です。出産は、正常分娩か無痛分娩、地域差などにより費用が変化しますが、約35万円から約70万円と多額の費用がかかります。そのため、この制度で経済的なサポートを提供しています。この一時金は、健康保険や国民健康保険に加入している被保険者(またはその扶養者)が受け取れるものです。
支給額は2023年4月から引き上げられ、1人につき 50万円(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)が支給されます。産科医療補償制度の対象とならない場合(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合、または妊娠22週未満の出産の場合)は、1人につき 48.8万円が給付されます。また、多胎妊娠の際には、子どもの人数に応じて同額が加算されるのが特徴です。例えば、双子を出産した場合は100万円が支給されます。
支給額は?
出産育児一時金の給付額は以下の通りです。
| 出産の状況 | 支給額 |
|---|---|
| 正常分娩 | 500,000円 |
| 産科医療補償制度の対象外(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合) | 488,000円 |
| 産科医療補償制度の対象外(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合) | 488,000円 |
| 双子以上の多胎出産 | 子ども1人につき 500,000円 |
対象者と条件
出産育児一時金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 健康保険または国民健康保険の被保険者(もしくは扶養者)であること。
- 妊娠4か月(85日)以上で出産(早産含む)。
- 国内での出産の場合(国外出産でも一定条件を満たせば対象)。
- また、流産や死産の場合でも妊娠4か月(85日)以上であれば対象となります。
一見複雑な制度ですが、ほとんどのケースで支給を受けられる条件を満たしています。
申請方法
出産育児一時金の申請方法は以下の3つの選択肢があります。
- 直接支払制度(主流の方法)
出産費用を病院が健康保険組合などに直接請求する仕組みです。この方法を選択すると、手当分の金額が差し引かれた状態で医療機関等に支払うことができ、自分で払い戻しの手続きをする必要がありません。
もし、出産費用が法定給付額500,000万円を超えなかった場合は、差額が支給されます。出産育児一時金差額申請書が送付されてきますので、忘れずに申請しましょう。
- 受取代理制度
被保険者が病院を代理として健康保険に請求する方法です。申請者は一時的な立て替えが必要ですが、後から支給金額が受け取れます。
- 償還払い制度
一旦全額を自己負担してから、健康保険組合に申請する方法です。この方法は手間がかかるため、他2つの方法が推奨されています。
必要な書類
申請方法により必要な書類は異なります。
【直接支払制度の医療機関等で出産の場合・全額出産費を支払った場合】
出産費用が50万円未満かにより、提出する書類が異なります。下記で、詳細を確認しましょう。
出産費用が50万円未満
- 直接支払制度を利用した場合:出産育児一時金等内払金支払請求書を提出しましょう。出産から2、3か月後に差額が受け取れます。
- 直接支払制度利用なしの場合:出産育児一時金等内払金支払請求書と添付資料が必要になります。
- 出産育児一時金等内払金支払請求書
- 医療機関から交付される直接支払制度不使用の同意書の写し
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し ※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、「産科医療補償度加入機関」のスタンプが押されたもの
- 医師又は助産師が発行した出生証明書等の写しか、又は市区町村が発行した戸籍謄本(抄本)
出産費用が50万円以上
- 直接支払制度を利用した場合:申請不要です。
- 直接支払制度利用なしの場合:2と同様の書類が必要です。
- 出産育児一時金等内払金支払請求書
- 医療機関から交付される直接支払制度不使用の同意書の写し
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し ※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、「産科医療補償度加入機関」のスタンプが押されたもの
- 医師又は助産師が発行した出生証明書等の写しか、又は市区町村が発行した戸籍謄本(抄本)
【受取代理制度の医療機関等で出産の場合】
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)の提出が必要です。※出産前に保険者へ提出が必要です。
よくある質問
Q: 出産育児一時金はいつ受け取れるの?
A: 申請から数週間後、本人の指定口座に振り込まれます。直接支払制度の場合は、出産費用を差し引いた金額を病院に支払うだけです。
Q: 制度の適用条件は変更されることがある?
A: 2023年4月に50万円へ引き上げされたように、支給額や条件は変更される可能性があります。最新情報を常にチェックしましょう。
まとめ
「出産育児一時金」は、出産時の費用負担を軽減する心強い制度です。出産する人数や状況によって給付額が増えるため、経済的な準備の負担を大幅に減らすことができます。直接支払制度を利用すれば、手続きがスムーズになり安心して出産に臨めるでしょう。
これから出産を迎えるご家庭は、対象者や申請方法をしっかり確認して、制度を最大限活用してください。必要な情報は早めに調べ、漏れのない申請を心掛けることが重要です。