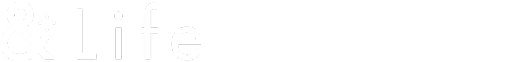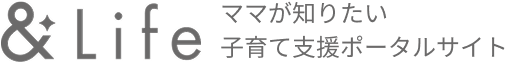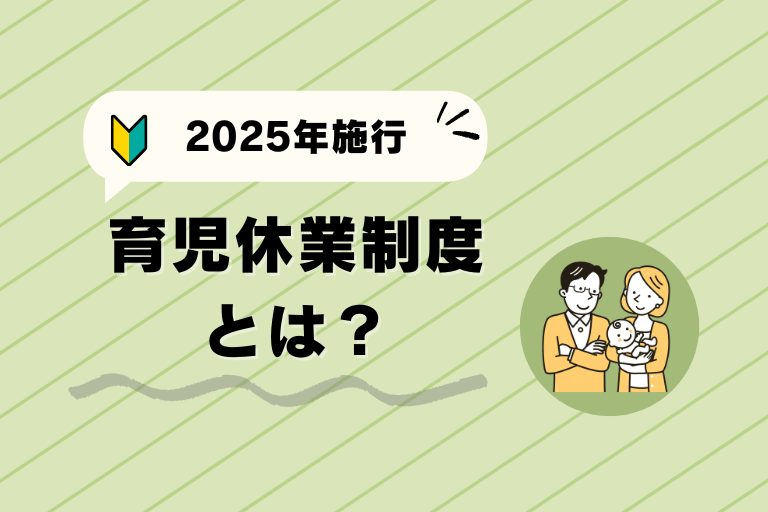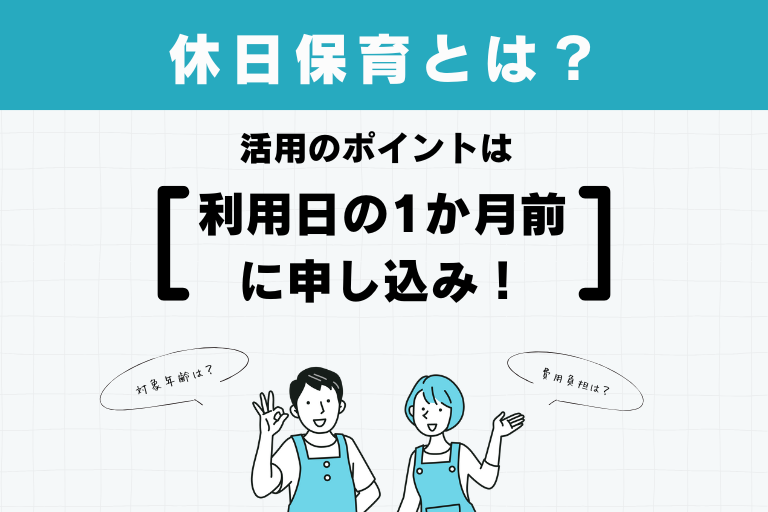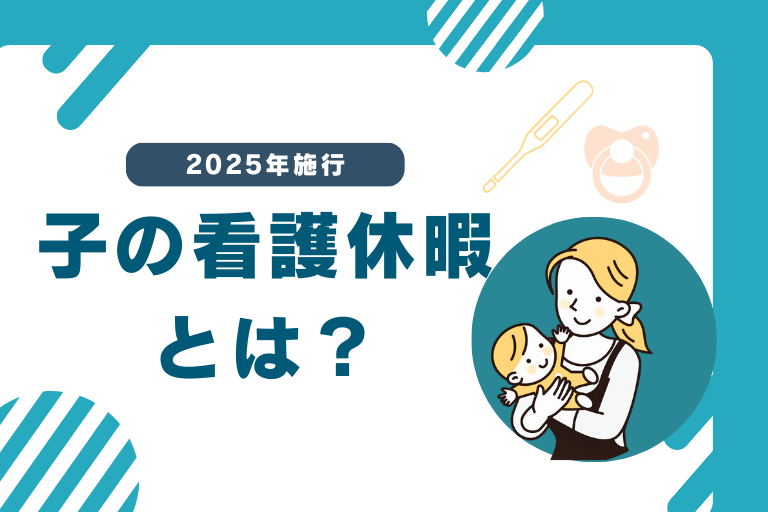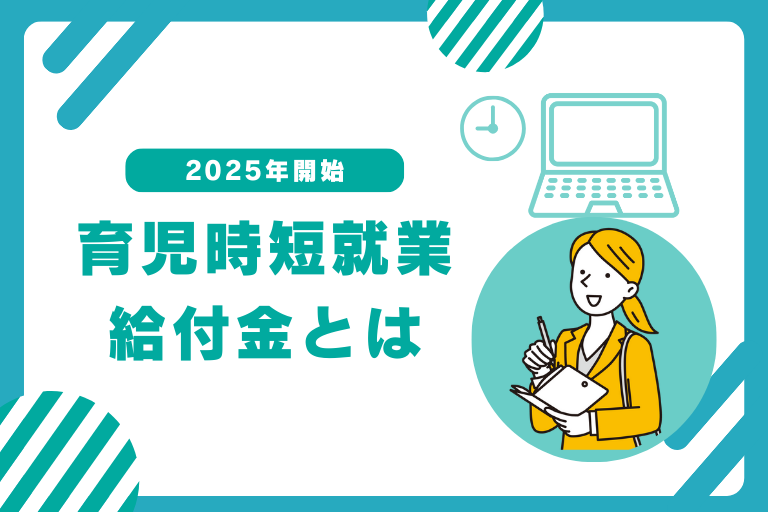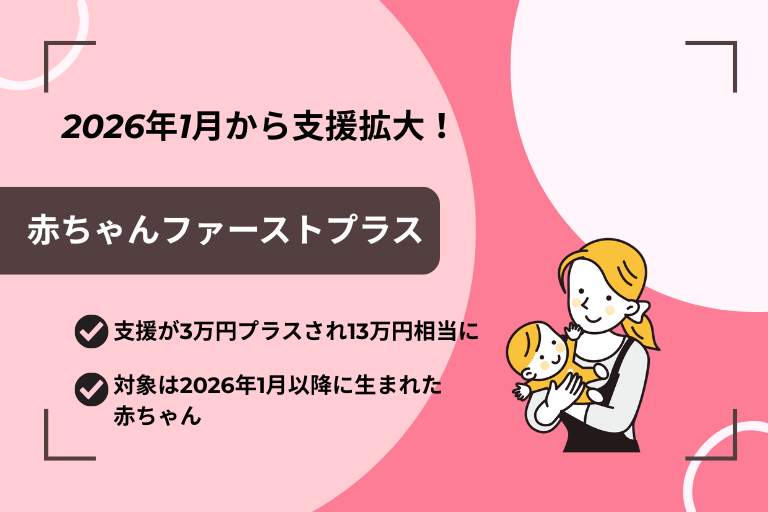仕事と子育てを両立するのはとても大変ですよね。そんな課題を解決する支援制度として「育児休業制度」があります。この制度は、赤ちゃんが産まれたり家族が増えた際に、仕事を一時的に休んで子育てに専念できる仕組みです。休業中には一定の収入が支給されるため、経済的な不安も軽減されます。さらに、2025年には制度が改正され、共働き家庭や男性の育休取得がより簡単になる予定です。育児休業制度の概要や利用方法、改正ポイントをわかりやすく解説します!
目次
1. 育児休業制度とは?

育児休業制度は、仕事と育児を両立するために働く親が一定期間休業できる、育児と仕事の両立支援制度です。この制度は育児・介護休業法によって定められ、日本国内で子育てを支援する重要な制度のひとつとなっています。
基本的な内容としては、下記の3つです。
- 子どもが1歳になるまで育児休業が可能(保育園に入れない場合などは最大2歳まで延長可能)。
- 男女を問わず取得可能で、共働き家庭や男性の育児参加を促進。
- 雇用保険から「育児休業給付金」が支給されるため、収入を確保しながら育児に専念できる。
育児・介護休業法によって、育児休業の取得が義務付けされているため、企業は対象者からの育児休業取得希望を拒否することはできません。
2. 取得条件は?
育児休業制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 雇用期間
現在の勤務先で1年以上勤務していること(派遣社員や契約社員も条件を満たせば取得可能)。 - 子どもの年齢
原則として1歳未満の子どもが対象。例外的に保育園に入園できないなどの場合は2歳になるまで延長が可能です。 - 契約形態の柔軟性
正社員に限らず、契約社員や派遣社員も条件を満たせば対象となります。
育児・介護休業法にまつわる各種制度は、必要なタイミングや子どもの人数による取得期間の違いなど、人によって内容が異なります。そのため、各種制度についての詳細は勤務先の担当部署に問い合わせるようにしましょう。
3. 育児休業制度の内容は?
具体的にはどんな支援内容となっているかご紹介。法改正により、2025年4月から段階的に施行された内容についても、解説していきます。
支援内容
- 育児休業:子が1歳(最長で2歳)に達するまでの間に取得できる休業です。
- 産後パパ育休(出生児育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる休業です。
- 短時間勤務等の措置:子が3歳までは、労働者が希望した際に短時間勤務(1日原則6時間)の措置が事業主に義務づけられています。
- 子の看護等休暇制度(※):子どもの病気や怪我で治療が必要な場合、医療機関への付き添いや看護のために休暇を取得できます。
- 時間外労働の制限:労働者が請求した場合、事業主は1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働を制限する義務があります。
- 不利益扱いの禁止:育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止とされています。
- 転勤についての配慮:事業主は労働者を転勤させる場合、育児の状況について配慮義務があります。
- 所定外労働(残業)の制限(※):子が3歳未満の場合、労働者は所定外労働を制限する権利を事業主に請求することができます。
- 深夜業の制限:小学校就学前までの子を養育している場合、深夜業を制限することを事業主に請求できます。
- 育児休業等に関するハラスメントの防止措置:上司・同僚による育児休業等の申し出、取得などによるハラスメント防止を事業主へ義務付けています。
※法改正による2025年4月1日以降段階的に施行
3. 2025年の改正ポイントの解説
具体的な支援内容については前述した通りですが、太字の箇所は、法改正により2025年4月1日以降段階的に施行される新しい内容となっています。下記で、詳しい内容を確認してみましょう。
ポイント1:子の看護等休暇
2025年4月1日より、さらに幅広い方が利用できる制度となっています。また、改正後には制度の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わりました。
【改正前】- 名称:子の看護休暇
- 対象年齢:小学校就学前
- 取得理由:病気・けが・予防接種・健康診断
- 対象外の労働者:(1)引き続き雇用された期間が6か月未満の方 (2)週の所定労働日数が2日以下の方
【改正後】
- 名称:子の看護等休暇に変更
- 対象年齢:小学校3年生終了までに延長
- 取得理由:従来の取得理由に感染症に伴う学級閉鎖など、入園式、卒園式を追加
- 対象外の労働者:週の所定労働日数が2日以下の方のみに変更され、改正前の(1)は撤廃
子の看護等休暇制度の具体的な休暇日数について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。
ポイント2:所定外労働の制限(残業免除)の子どもの対象拡大
請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となる子供の対象年齢が拡大査、家庭と仕事の両立の実現に役立てられます。
【改正前】
対象年齢:3歳に満たない子を養育する場合
【改正後】
対象年齢:小学校就学前の子を養育する労働者
ポイント3:テレワーク導入の努力義務化
- 3歳未満の子を養育する労働者に関して、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加されます。
- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように、必要な措置を講じることが事業主に努力義務化されます。努力義務化では、法的拘束力や罰則はありませんが、労働者からの意見を聞き実施することが求められます。
ポイント4:育児休業における取得状況の公表義務が拡大
育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられる企業の範囲が広がりました。これにより、育児と仕事の両立を目指している労働者にとって、働き方とのギャップを生じさせないための、指標の1つとして企業の選択がしやすくなると思われます。
【改正前】
公表が義務付けられている企業:従業員数1,000人超の企業
【改正後】
公表が義務付けられている企業:従業員数300人超の企業
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。
これにより、育児と仕事の両立を目指している労働者にとって、働き方とのギャップを生じさせないための、指標の1つとして企業の選択がしやすくなると思われます。
企業による公表は、インターネットなどによる一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」では、12万社以上が公表しています。
※育児休業等とは、「育児休業(産後パパ育休を含む)」および「短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置」または「小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務措置に基づく休業」のことです。
産後パパ育休(出生児育児休業)の給付面について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
ポイント5:柔軟な働き方を実現するための措置等が義務に
2025年10月から施行され、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置が企業に求められます。
具体的には、以下5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずることが必要となります。
講ずべき5つの選択肢
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
労働者は、企業が講じた2つ以上の措置から1つを選択し、利用できます。
企業からの周知方法も定められていますので、対象の方は提示された内容を確認するようにしましょう。
周知方法
周知時期
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
例)1歳8か月に達する日の3日後~2歳8か月に達する日の1日後まで
周知事項
- 事業主が上記で選択した対象処置(2つ以上が必要)の内容
- 対象処置の申出先
- 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度の詳細
個別周知・意向確認の方法
- 面談(オンライン可)
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等のいずれか
ポイント6:個別の意向聴取・配慮が義務に
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、子や各家庭の状況に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取することが義務化されています。
意向聴取方法
意向聴取の時期
- 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
- 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
例)1歳8か月に達する日の3日後~2歳8か月に達する日の1日後まで
聴取内容
- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- 勤務地(就業の場所)
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法
- 面談(オンライン可)
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等のいずれか
さらに、配慮に当たって、以下のような対応をすることも望ましいと、厚生労働省のウェブサイトでは説明されています。
- 子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること。
- ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等。
まとめ
「育児休業制度」は、働きながら子育てを支える重要な仕組みです。育児・介護休業法の2025年制度改正では、柔軟性の向上や男性育休の促進など、利用しやすい制度へと進化しています。この制度を活用することで、子育てと仕事を両立しながら家族全員が安心して育児に専念できる環境を整えましょう。
対象者や申請条件を確認し、自分の家庭に合った使い方を検討することも大切です!最新情報や詳細は、厚生労働省の公式サイトを参考にしてください。
※本記事は2025年9月現在の情報に基づき作成しています。最新かつ詳細な情報は、厚生労働省のウェブサイトやお住まいの自治体窓口、企業の担当部署にご確認ください。
出典:
・厚生労働省 育児休業制度とは | 育てる男が - イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system
・厚生労働省 育休休業制度 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html