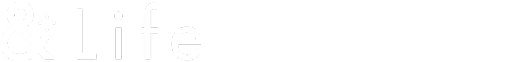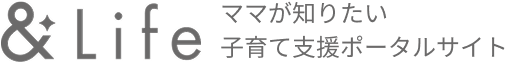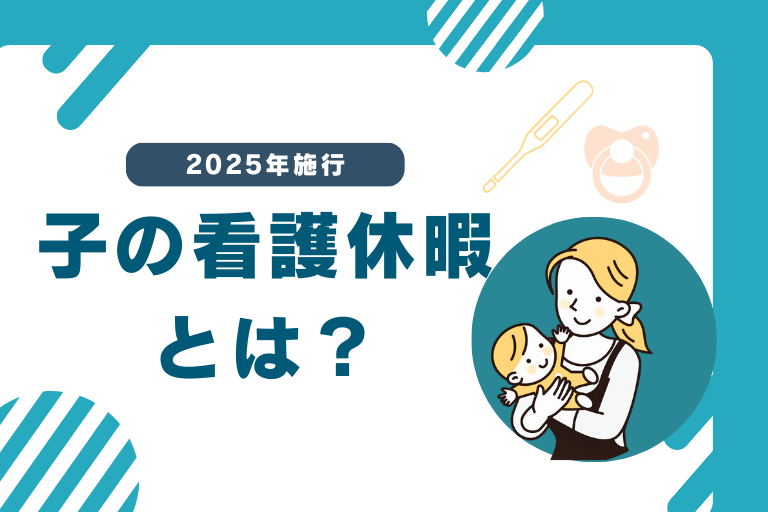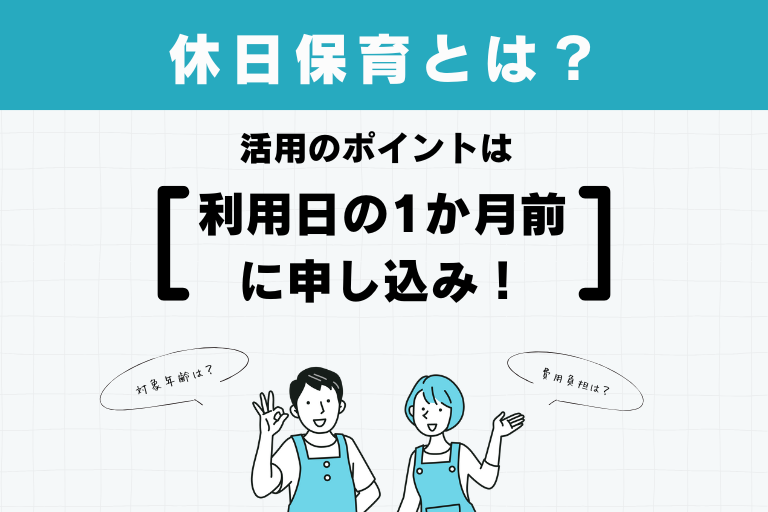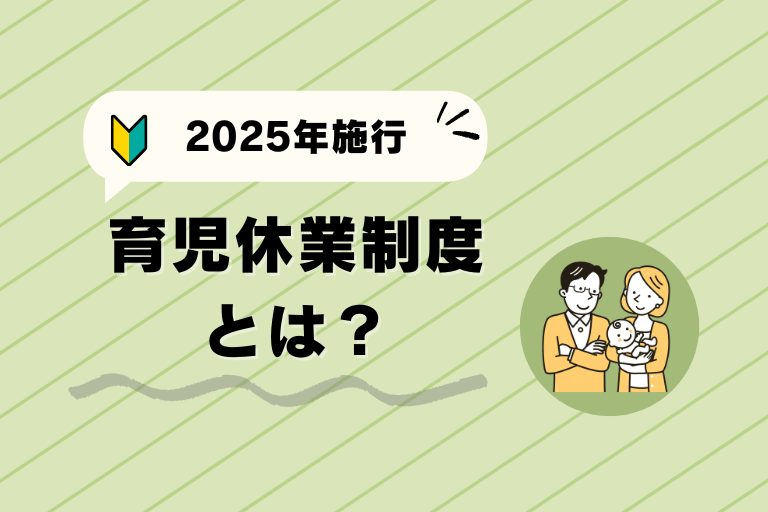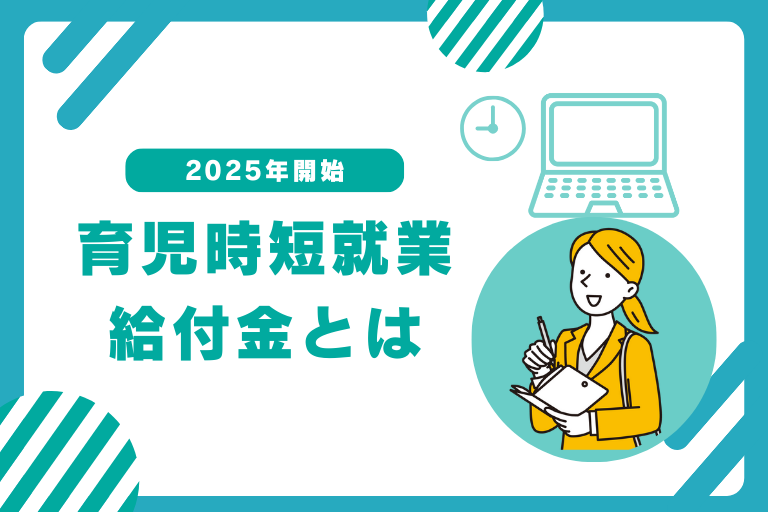親として子どもの病気や怪我はどうしても避けられないもの。仕事をしつつ、うまく両立をしなければなりません。そんな時に頼れるのが『子の看護等休暇制度』です。働く親が子どものケアを優先できるよう、法律で守られた仕組みを紹介します。この記事では子の看護等休暇制度の特徴や取得条件、給与設定、具体的な使い方を詳しく解説します。
目次
1. 子の看護等休暇制度とは?
子の看護等休暇制度は、働く親が病気や怪我をしている子どもの看護や予防接種・健康診断を受けさせる際に有給または無給で休暇を取得できる休暇制度です。この制度は、育児・介護休業法で定められている法定休暇であり、対象者からの申し出があった場合、企業は休暇取得を与えるもしくは看護休暇での欠勤として扱います。
2. どんな特徴があるの?

子の看護等休暇制度の特徴
- 子どもへの看護時間を確保
- 予防接種・健康診断への対応
- 企業に時季変更権がない
- 無給または有給の給与扱い
子どもの病気や怪我で治療が必要な場合、医療機関への付き添いや看護のために休暇を取得できます。
子どもの健康維持のための活動(予防接種や定期健診)についても、この制度を利用できます。
年次有給休暇で認められている、休暇の取得時季の変更を命じることのできる時季変更権ですが、子の看護等休暇制度には適用されません。そのため、労働者の申し出のタイミングで取得が可能です。
看護休暇が有給に設定されている企業もあります。多くの場合は無給ですが、就業規則によって異なります。また、休暇によって不利な扱いを行うことは禁止されているため、給与等の査定において、看護休暇の取得による減額や賞与や昇給への影響は禁止とされ、厚生労働省の指針において、企業はその旨を給与規定に定めることが求められます。
子の看護休暇制度(2025年3月まで)の改正について
育児・介護休業法の改正に伴い、子の看護休暇制度(2025年3月まで)が見直され、2025年4月1日に改正されて施行されています。先述した特徴からさらに、育児と仕事を両立する内容が拡充されています。改正後の詳細を改正前と比較してみましょう。
| 改正前 | 改正後(2025年4月~) | |
|---|---|---|
| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
| 対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了までに延長 |
| 取得理由 | (1) 病気・けが (2) 予防接種・健康診断 | (1) 病気・けが (2) 予防接種・健康診断 (3) 感染症に伴う学級閉鎖 (4) 入園(入学)式、卒園式 ※(3)、(4)を追加。 |
| 労使協定の締結により除外できる労働者 | (1) 引き続き雇用された期間が6か月未満 (2) 週の所定労働日数が2日以下 | (1) 週の所定労働日数が2日以下 ※改正前⑴は撤廃。 |
対象者はどんな人か?
- 子育て中の労働者:小学校3年生までの子どもを養育している保護者で、労働契約がある方が対象です。
- 正社員のみならず、契約社員、パート、アルバイトも制度を活用できます。
性別を問わず取得可能:父親も母親も利用できます。
ただ、「週の所定労働日数が2日以下」や「日雇い」の労働者の方は、本制度の適用対象外となります。
取得例では、どんな状況で取得しているかをご紹介します。
取得例:
フルタイム勤務の母親が子どもの風邪の看護で2日間休暇を取得する。
父親が子どもの定期健診への付き添いのために、半日単位で休暇を利用する。
取得日数は?
子の看護等休暇制度の取得日数は以下です。
子どもが1人:5日(1年あたり)
子どもが2人以上:10日(1年あたり)
取得日数は2人以上であれば、10日取得することが可能です。3人や4人の子どもがいたとしても、上限は10日となります。しかし、企業独自に10日より多い日の取得を認めていることもありますので、取得日数は企業判断の範囲となります。
3. 給与設定は?

子の看護等休暇制度の給与は、企業ごとの規定によって異なります。以下が基本的な考え方です。
無給の場合
労働基準法に基づき、欠勤として処理されることが一般的です。ただし、社会保険料や年金の積立に影響はありません。
無給の日数計算方法:月給250,000円の場合、1日分の給与が約12,500円(250,000円÷20日)。欠勤日数に応じて控除額が決まります。
有給の場合
企業が独自制度として有給扱いを設けている場合、賃金は通常の給与として支払われます。
有休の日数計算方法:通常勤務日と同じ計算式で支払われます。
4. 申請方法は?
子どもの看護は急に必要となることが多いため、取得における申請は電話口での口頭確認でも取得できます。
必要な申請手続きや診断書の提出は出社後にまとめて行うのが一般的です。子の看護等休暇の申請方法については、企業ごとに申請方法が変わっていますので、就業規則を確認し不明な場合は勤務している企業の労務担当者に問い合わせてみましょう。
まとめ
「子の看護等休暇制度」は、働きながら子育てをする家庭にとって非常に頼りになる制度です。病気や怪我の子どもを安心してケアできるよう、法律で守られた仕組みが整っています。また、2025年以降は改正によって利用範囲が広がっているため、利用方法についても改めて確認しておくのがいいでしょう。看護休暇制度を活用し、子育てと仕事の両方で充実した日々を目指しましょう!
出典:
・厚生労働省 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html
・厚生労働省 Ⅳ子の看護等休暇制度