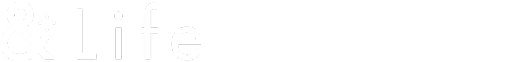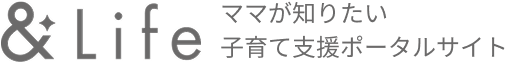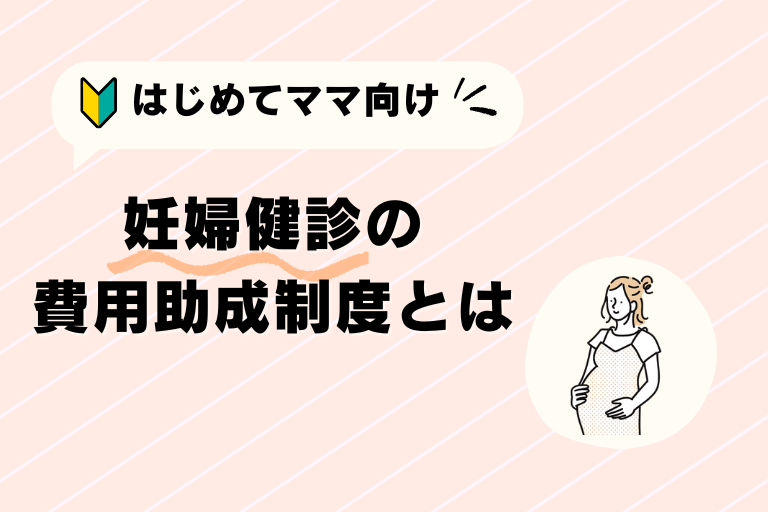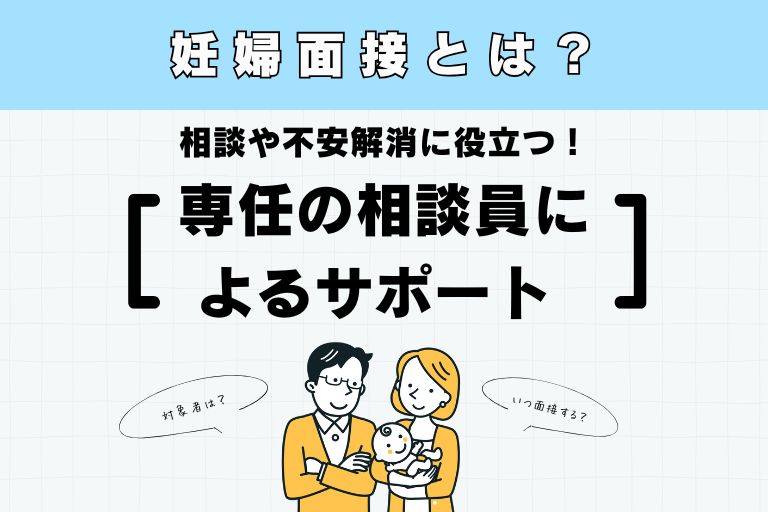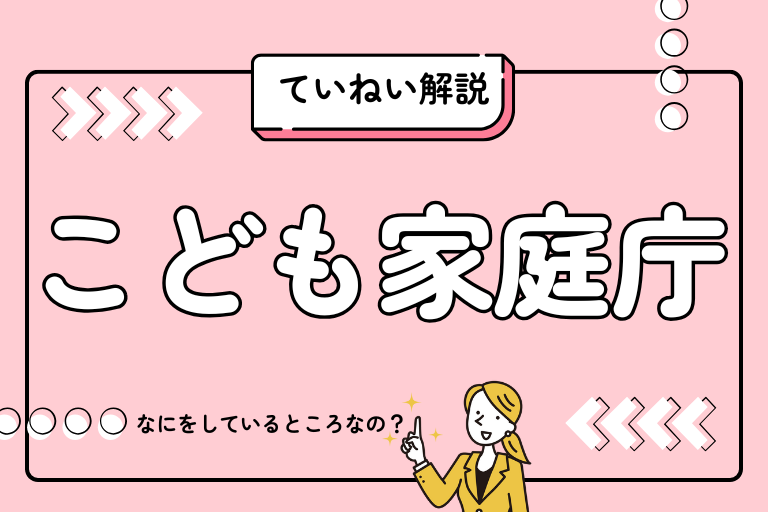お腹の赤ちゃんを迎える準備、楽しみだけど不安もたくさんありますよね。「妊婦のための支援給付」は、そんな妊婦さんの経済的な負担や妊娠による不安の軽減を目的とした制度です。この記事では、給付金の内容や対象者、申請方法について詳しくご紹介します。初めての妊娠時や困り事、不安がある方は、ぜひ活用してみましょう。
妊婦のための支援給付とは?

「妊婦のための支援給付」とは、妊娠中から出産、子育て期間にわたり、経済的・精神的負担を軽減するための切れ目のない支援を実現するための給付金制度です。これは2025年4月1日から「子ども・子育て支援法」という法律の改正をもとに、国が提供する給付金であり、すべての母親に安心して妊娠、出産、子育てをしてほしいという目的があります。
この支援の特徴として、妊娠している方への給付金のみならず、相談窓口などで面談を一緒に実施することにより、妊娠中の不安や困りごとの相談が可能となっている点です。相談に応じて制度やサービスを紹介してもらえるため、不安解消に役立ちます。
※2022年度補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」を2025年度から法律に基づく制度として移行し創設されています。そのため、移行前の「出産・子育て応援ギフト」を申請している場合は申請できません。
対象者
「妊婦のための支援給付金」の対象者は以下の条件を満たす方です。
- 日本国内に住所を有している妊婦の方。(お住まいの自治体への住民登録が必要となります。)
- 妊娠届を提出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた方。
- 医療機関の医師等による胎児心拍の確認を受けた方。
- 出産・子育て応援交付金事業による現金やクーポン等の支援を受けていない方。
※医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。
※胎児心拍の確認後に流産・死産・人工妊娠中絶された方、出産後にお子様を亡くされた方につきましては、妊婦支援給付金1回目・2回目の支給対象となります。
給付金額・申請期間
給付額はどの自治体でも一律で、基本的には1回目と2回目の金額を合わせて10万円です。
ただし、双子の場合は2回目の給付金額が増額されます。
| 妊娠支援給付金(1回目) | 妊娠支援給付金(2回目) | |
|---|---|---|
| 給付額 | 50,000円 | 妊娠している子ども1人当たり 50,000円※1 |
| 申請可能期間※2 | 妊婦給付認定後~2年以内 | 出産予定日の8週間前から2年以内(出産予定日前に出産、死産、流産又は人工妊娠中絶した場合はその日から2年以内) |
| 支給時期※3 | 申請から1~2か月後 | 申請から1~2か月後 |
※1 双子を妊娠している場合、1回目に50,000円、2回目に100,000円の計150,000円が支給されます。
※2 各自治体により、申請方法が異なりますので詳しい申請方法は、各自治体のホームページを確認し、問い合わせましょう。
※3 支給時期についても各自治体により異なり、数か月後になる可能性もあります。申請忘れがないよう、早めに申請しましょう。
給付までの流れ
妊婦支援給付金を受け取るための基本の流れは以下の通りです。
1. 妊娠届を提出する
医療機関で確定診断を受け、妊娠が判明したら、住民票のある役所や保険センターへ妊娠届を提出します。この際に給付に関する案内が行われます。
2. 申請書の入手・記入
自治体の窓口またはWebサイトで妊婦給付認定申請書を入手します。本人確認書類や口座情報などの準備が必要になります。給付金は、妊婦さん本人名義の金融機関口座に限られていますので、注意が必要です。
3. 申請前に面談を受ける
妊婦面談により、妊娠している女性の不安解消や包括的なサポートをしてくれます。また、自治体によっては妊婦面談後に申請書の案内が行われる場合もあります。
※妊婦面談は必須ではありませんが、申請書の提出前後で案内される自治体がほとんどです。少しでも不安や困りごとがある場合は活用しましょう。
4. 施設窓口へ提出
自治体の窓口や郵送形式、Webサイトで申請書類を提出します。
5. 審査・給付金支給
審査により、条件を満たしていると認められた場合は、指定された口座へ給付金が振り込まれます。給付までの期間は自治体によって異なりますが、一般的には申請後1〜2か月程度が目安となります。
まとめ
「妊婦のための支援給付金」は、経済的な負担を軽減するだけでなく、安心して妊娠・出産・育児をしたい妊婦にとっても心強い制度です。事前にしっかり調べて準備することで、不安を減らし子育てに専念できる環境を整えましょう。
本記事は2025年7月時点の情報です。最新の情報や詳細については、お住まいの自治体のウェブサイトや窓口などでご確認ください。