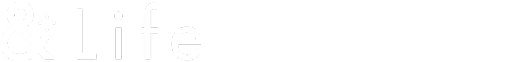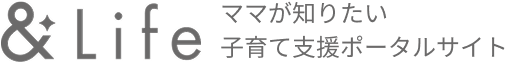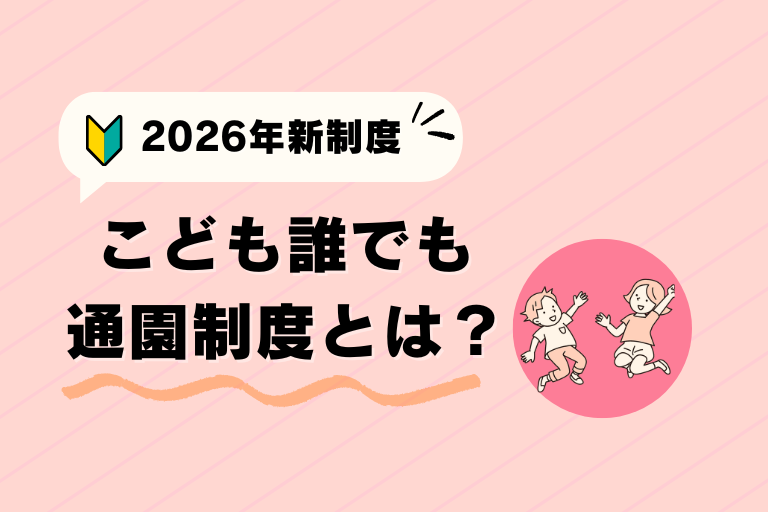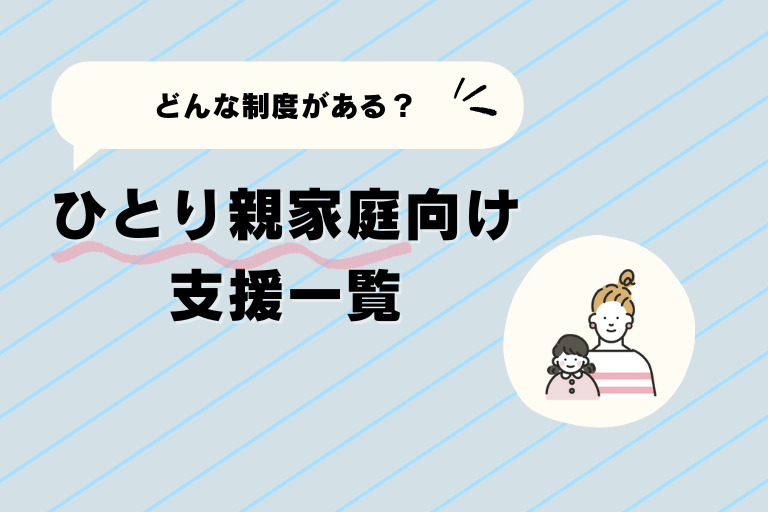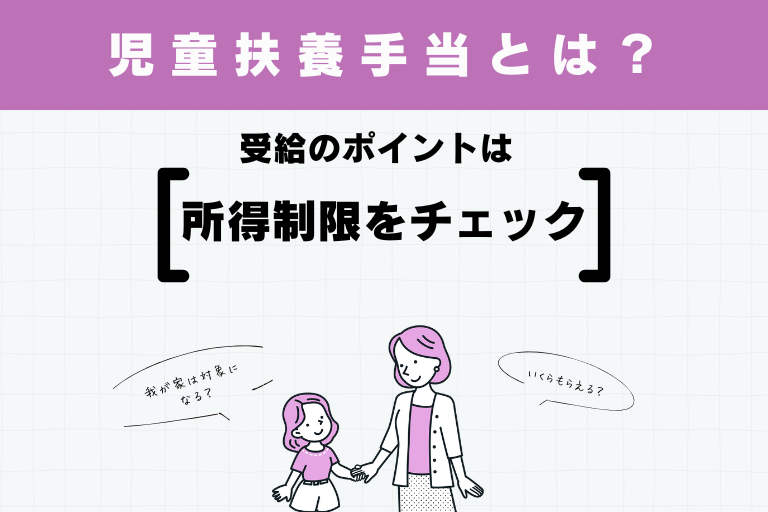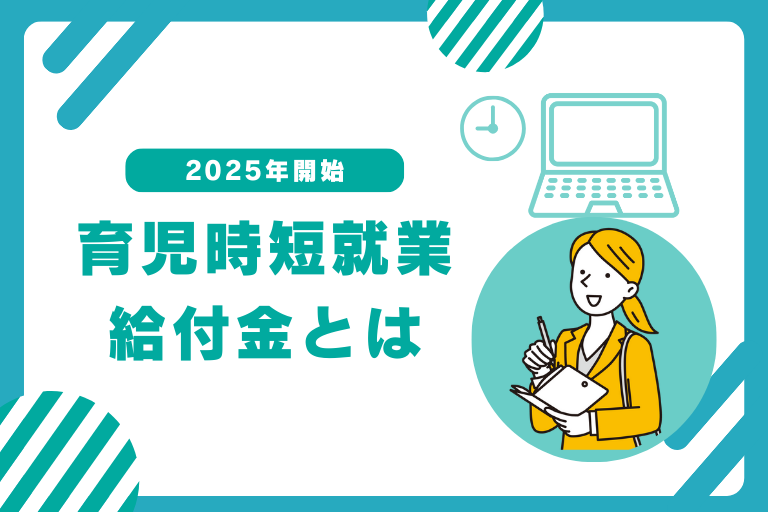保育園探しで悩んだ経験のあるパパママのみなさんへ!『こども誰でも通園制度』が新たに創設され、2026年から本格導入されます。この制度は、名前の通り“誰でも通える保育園”を実現する取り組みで、2歳までの未就園児を対象とした制度です。この記事では、一時預かり保育制度との違いや具体的な内容について詳しくご紹介します。
目次
「こども誰でも通園制度」とは?

「こども誰でも通園制度」は、こども未来戦略に基づき、2026年から本格運用される予定の新しい保育支援制度です。この制度は、これまでの保育園や幼稚園の利用時に発生していた制約を大幅に緩和し、「すべての子どもが自由に通園できる環境」を目指しています。
具体的には、1か月あたりの利用上限の中で、0歳6か月から満3歳未満までの未就園児を対象に、保育園や認定こども園で一時的に預かってもらえる制度となっています。特に、保育施設への預かり理由は必要なく、多様な働き方やライフスタイルにとらわれない支援を目的としています。
現在の日本社会で問題になっているのが、少子化による人口減少。それに伴い働き手不足が懸念される中、子育て世帯の負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境を整えることが急務とされています。「こども誰でも通園制度」は、そんな課題を解決するための一歩として導入される新しい制度と理解しておきましょう。
「こども誰でも通園制度」の特徴

「こども誰でも通園制度」が新たに導入されることで、以下のような変化が期待されています。
1. 保育施設利用のハードルを下げる
これまで保育施設を利用するためには、保護者が働いているなどの一定の条件を満たす必要がありました。しかし、こども誰でも通園制度では、保護者が希望すれば理由を問わず利用できます。
2. 経済的負担の軽減
利用料は1時間あたり200~300円程度が見込まれています。これは、国や自治体の税金(公費)や、社会全体から集める「子ども・子育て支援金」(支援納付金)を財源にあてることで、利用する家庭が実際に支払う料金が抑えられる仕組みです。そのため、さまざまな家庭が費用の心配をあまりせずに利用しやすくなります。ただし、最終的な利用料や助成の内容は自治体によって異なる場合があるため、今後発表される正式な案内を確認する必要があります。
3. 施設の利用範囲の拡大
全国全自治体(1,718自治体)での導入が想定され、保育園・認定こども園・地域型保育事業所・幼稚園など、さまざまな場所での利用が可能になる見通しです。
「こども誰でも通園制度」の保育形式
「こども誰でも通園制度」では、子どもたちの多様な保育ニーズに対応するため、以下のような形式が採用されることが一般的です。
1. 一般型(在園児と合同)
一般型は、通常の在園児と一時的に利用する子どもが一緒に保育を受ける形式です。すでに運営されている園の定員に関わらず、こども誰でも通園制度で制定された上限人数まで受け入れてもらえます。定員は園によって自由に設定がされます。
メリット- 在園児と年齢や状況に関わらず関われるため、子どもが社会性や協調性を育む機会が得られる。
- 施設側にとってフレキシブルな運用が可能。
2. 一般型(一時預かり専用施設)
一時的な保育ニーズのある子ども専用のスペースを使用する形式で、在園児とは別の室内スペースとなります。専任の職員が決められるため、既存の園児を含む利用定員に影響しません。
メリット- 短期的な利用に特化しており、家庭の急なニーズに対応しやすい。
- 個別対応が受けられるケースが多い。
- 在園児への負担を軽減しながら受け入れが可能。
3. 余裕活用型
利用定員に達していない保育施設が、定員の範囲内で受け入れを行う形式です。在園児と一緒に保育されることで、環境が変わり子どもの成長を育む機会にもなります。
メリット- 在園児と年齢や状況に関わらず関われるため、子どもが社会性や協調性を育む機会が得られる。
- 施設側の職員確保がしやすい。
一時預かり保育との違いは?
「こども誰でも通園制度」と類似している制度に「一時預かり事業」という制度があります。こちらも、一般的には生後57日目から小学校就学前まで(施設により異なる)を対象に、保育施設での預かり保育をしてくれます。ただし、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった未就園児である乳幼児を対象としている点に注意が必要です。
| こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 | |
|---|---|---|
| 目的 | 子どもの保育の平等化と家庭の負担軽減 | 一時的に保育が必要な場合に利用できるサポート事業 |
| 対象者 | 0歳6か月~満3歳未満の未就園児 | 家庭での保育が一時的に困難な乳幼児(親の病気、冠婚葬祭など) |
| 実施場所 | 保育園、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、地域子育て拠点など | |
| 利用頻度 | 1か月あたり10時間程度の上限を想定※1時間単位等で利用 | 利用制限なし ※1日数時間から利用可能 |
| 利用料 | 1時間あたり200〜300円程度 ※利用者が時間単位で料金を支払う必要がある場合が多い | 1時間あたり200〜400円程度 |
| 利用方法 | 「総合支援システム(仮称)」を通して面談予約・日程調整を想定 | Webや窓口、事業者へ直接連絡することによる予約 |
| 実施自治体 | 1,718か所(すべての自治体) | 1,269か所(全自治体の約74%) |
| 実施方法 | ・一般型・余裕活用型 | ・一般型・余裕活用型 ※障害のある子については居宅訪問型の利用が可能 |
| 人員配置 | 0歳児3人につき保育従事者1人以上 1〜2歳児6人につき保育従事者1人以上 | 保育園の配置基準と同じ人数 |
「こども誰でも通園制度」は長期的な通園のための制度であり、子どもが継続的に保育施設を利用できる環境を整えます。一方、「一時預かり事業」は短時間や緊急時の保育が必要な家庭向けのサポートで、主に柔軟性を重視した使い方が目的です。それぞれの制度を用途に応じて使い分けることで、子育ての負担を軽減できます。
こども誰でも通園制度の利用方法

以下のステップで制度の利用が可能となる予定です。全国での本格的な始動は2026年と予定されており、現在は118の自治体が試験的に運用しています。試験運用の対象地域にお住まいの方は、お住まいの自治体へお問い合わせしてみてください。
1. 利用申請
お住まいの市区町村が定める方法で申請。利用認定後、「総合支援システム(仮称)」で子どもの情報を登録。
2. 事業所を探す
自治体に表示されている事業所から場所を選択する。
3. 初回面談
利用を希望する実施事業所と初回面談を行い、利用する子どもの特徴を把握してもらう。
4. 利用
登録情報と面談で把握した特徴をもとに、安心安全な利用が可能となる。
今後の期待と課題
「こども誰でも通園制度」は、待機児童問題の解消や子育て世帯の負担軽減に大きな期待が寄せられています。しかし、新しい制度が成功するためには以下の課題もあります。
- 保育士不足の解消:施設利用者の増加に伴い、保育士の確保が急務となります。
- 財源の安定確保:支援納付金や公費を充当するものの、持続的な財源確保が必要です。
- 地域間対応の調整:地方自治体ごとの格差や運用方法の違いを解消するための連携が重要です。
まとめ
「こども誰でも通園制度」は、すべての子どもが平等に保育施設を利用できる環境を整備する、画期的な制度です。従来の保育制度と比較して、入園審査の緩和や経済的負担の軽減、施設利用の幅広い対応が期待されます。運用が始まったら具体的な内容や詳細を自治体で確認し、制度を最大限活用していきましょう!
本記事は2025年7月時点の情報です。最新の情報や詳細については、お住まいの自治体のウェブサイトやお問い合わせ窓口などでご確認ください。
出典:
・こども家庭庁 こども誰でも通園制度
・こども家庭庁 こども誰でも通園制度について