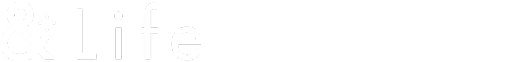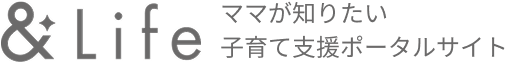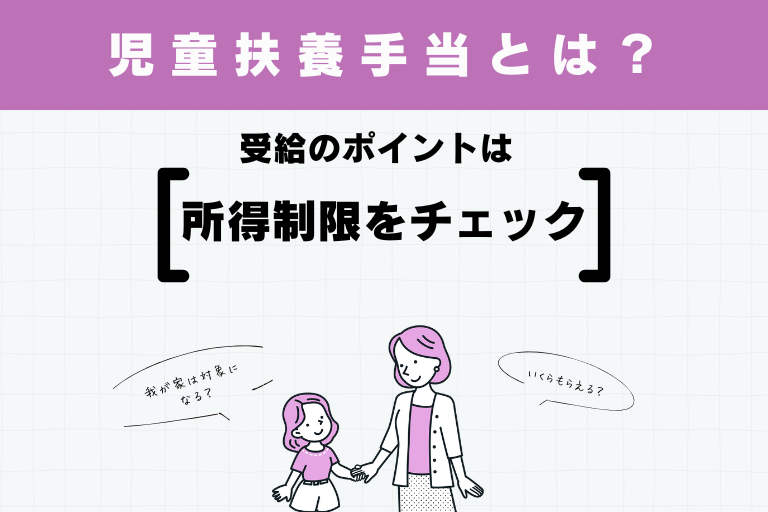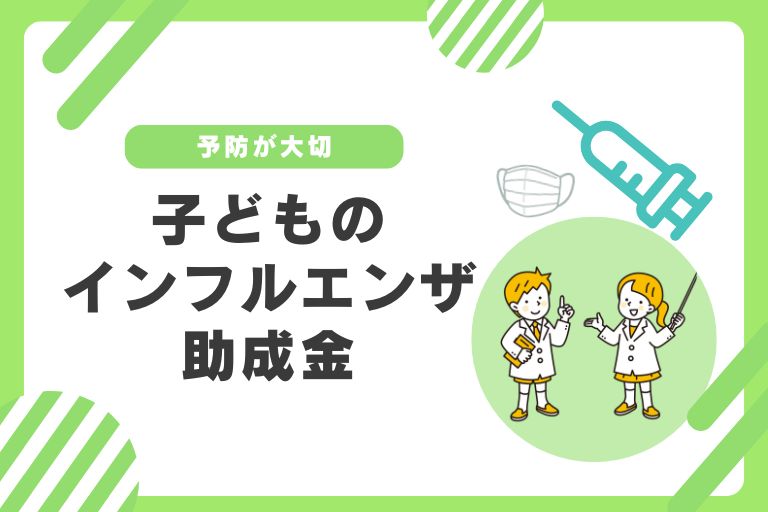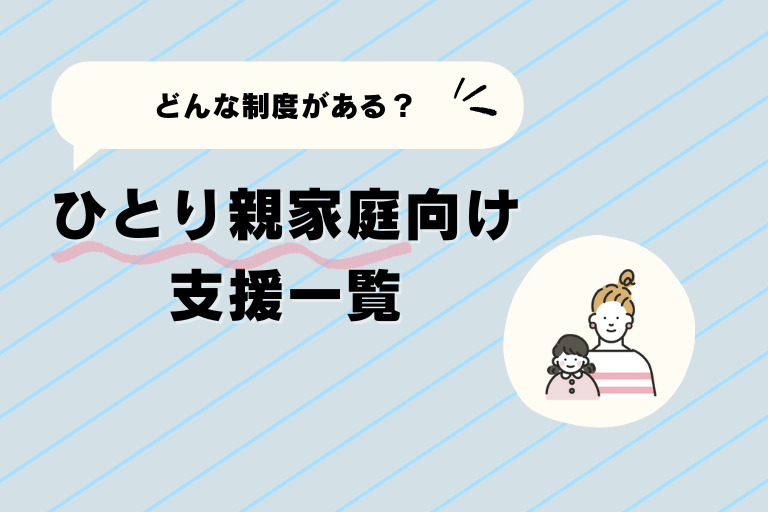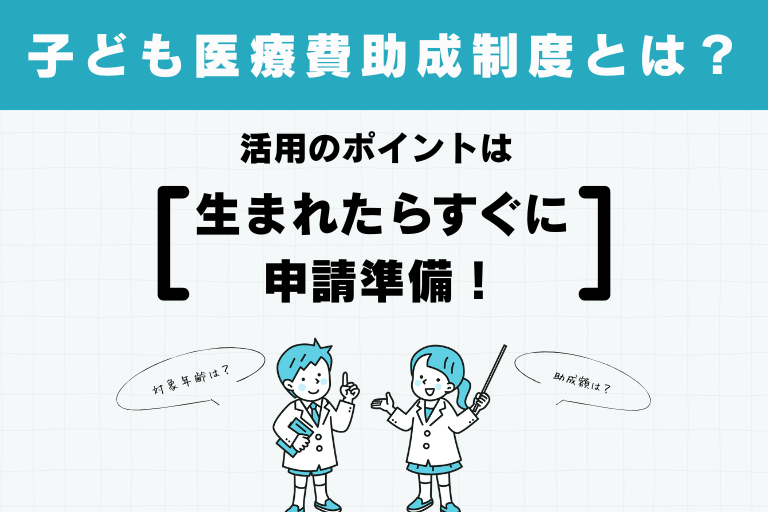毎日の子育て、本当にお疲れ様です。ひとり親として頑張る皆さんにとって、経済的不安は大きな心配事かもしれません。しかし、一人で抱え込む必要はありません。そんな家庭を支える制度が「児童扶養手当」です。この記事では、制度の内容、対象者、申請から受給までを分かりやすく解説します。不安が少しでも軽くなり、安心して手続きを進めるきっかけになれば嬉しいです。
児童扶養手当とは?ひとり親に寄り添う国の支援
児童扶養手当は、ひとり親家庭などで子どもを育てている方の生活を支え、子どもの成長を応援するための制度です。
簡単に言えば「父母の離婚などで片方の親と暮らしていない児童を育てる家庭の生活安定と自立を促し、福祉の増進を目的に支給される手当」です。
こども家庭庁が管轄し、国が設けた大切な支援策の一つです。
対象者を確認!誰がもらえる?
手当には「児童」と「養育者」それぞれに条件があります。
<児童の条件>
- 原則18歳に達する日以降最初の年度末(3月31日)まで対象
- 一定の障害がある場合は20歳未満まで対象
<養育者の条件>
以下の児童を監護する母、父、または養育者が対象です。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父母の一方に一定程度の障害がある場合
- 婚姻(事実婚を含む)によらず生まれた児童 など
なお、所得制限など詳細条件もあります。不安な場合はお住まいの自治体窓口で確認しましょう。
「児童手当」との違い
名前は似ていますが全く別の制度です。
- 児童手当:国内の子育て世帯すべてが対象。子どもの育成を社会全体で応援する制度。
- 児童扶養手当:ひとり親などを対象とし、所得制限は児童手当より厳格。
条件を満たせば両方受け取れますので違いを理解しておきましょう。
支給額と所得制限をチェック
児童扶養手当の支給額は、受給者ご自身や扶養義務者(児童の祖父母など)の前年の所得によって決まります。
所得が一定額未満の場合は「全額支給」、一定額を超える場合は「一部支給」となります。この一部支給にも所得の上限が設けられており、所得が増えるにつれて手当額は少なくなっていき、上限を超えると手当が支給されなくなります。
具体的な手当月額は、以下の通りです(令和7年9月現在の目安額) 。
児童扶養手当月額
| 子どもの人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
| 1人目 | 4万6,690円 | 4万6,680円~1万1,010円(所得に応じて変動) |
| 2人目以降加算(児童1人当たり) | 1万1,030円 | 1万1,020円~5,520円(所得に応じて変動) |
この手当を受けるための所得制限について、詳しく見ていきましょう。
所得制限額は、申請者の扶養親族等の数によって異なります。具体的な所得制限限度額は以下の通りです(令和7年9月現在の目安)。
児童扶養手当 所得制限限度額表 (申請者本人)
| 扶養親族等の数 | 全部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得) |
| 0人 | 69万円 | 208万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 |
※所得は収入から各種控除を差し引いた額を指します。
※扶養義務者(同居の祖父母など)にも所得制限があります。
※扶養義務者配偶者(父又は母が障害の場合)、孤児等の養育者は所得上限額が異なりますので、自治体に確認しましょう。
※扶養親族数とは?
- 母と子で2人暮らしの場合
- 母・子・無職の祖母で暮らしている場合
- 母と子で暮らしているが、子が元夫の扶養に入っている場合
→ 子どもが母の扶養に入っているので「扶養親族は1人」
→ 子と祖母を母が扶養していれば「扶養親族は2人」
→ 母の扶養には誰もいないため「扶養親族は0人」
申請から受給まで
<支給期間>
原則18歳に達する日以降最初の年度末まで。障害がある児童は20歳未満まで。
<支給方法>
指定口座へ年数回に分けて振込。
<申請窓口>
市区町村役場の「子ども家庭課」「福祉課」など。
<主な必要書類>
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書
- 通帳の写し
- 個別の状況に応じた書類(例:離婚調停証明)
まずは窓口で必要書類を確認してから準備しましょう。
申請後に知っておきたいこと
- 現況届の提出:毎年8月頃、継続受給のため必須。
- 変更届出:再婚、施設入所、転居などは速やかに届出。怠ると返還を求められる場合も。
- 制度改正の可能性:支給額や制度内容は見直されるため、最新情報を確認しましょう。
まとめ
児童扶養手当は、子どもと家庭を支える大切な国の制度です。手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、未来のための一歩です。
困ったときは一人で抱え込まず、必ず自治体窓口や地域の相談機関に相談してください。
※本記事は2025年9月現在の情報に基づき作成しています。最新かつ詳細な情報は、こども家庭庁のウェブサイトやお住まいの自治体窓口でご確認ください。
出典:こども家庭庁「児童扶養手当について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate