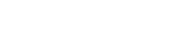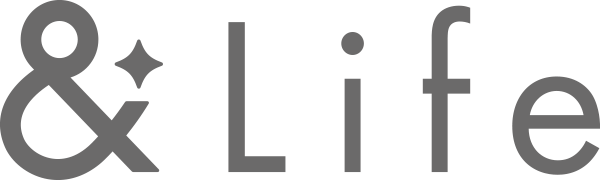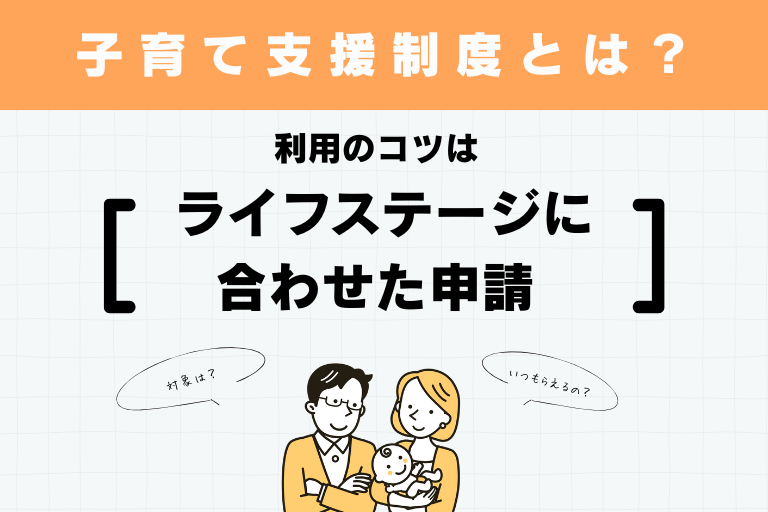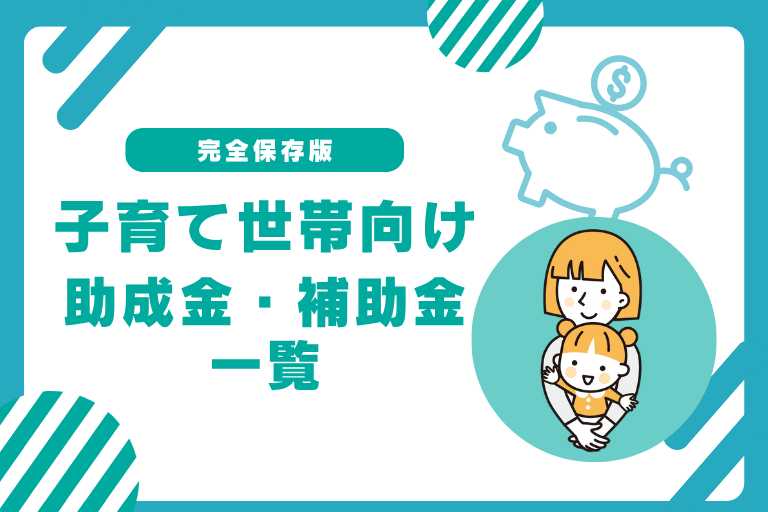子育て家庭には、国や自治体が提供するたくさんの支援制度があります。それらをうまく活用することで、経済的負担を減らしたり、育児のストレスを軽くしたりすることができます。しかし、「どのタイミングで、どんな制度が使えるかわからない……」という声も多いのではないでしょうか?
この記事では、比較的全国で利用できる妊娠中から中学生期まで、子どもの成長段階に合わせて利用できる子育て支援制度をわかりやすくまとめました。ぜひ最後まで読んで、あなたの家庭にぴったりの制度を見つけてみてください!
子育て支援制度とは?

子育て支援制度の目的
子育て支援制度は、子育て家庭や妊娠中の女性をサポートするために国や地方自治体が提供するサービスや助成金のことを指します。主に以下の目的で実施されています。
- 子育ての経済的負担を軽減する。
- 働きながら子育てを両立する家庭を支援する。
- 健康管理や育児不安を解消する。
- 地域全体で子育て家庭をサポートする。
これらの制度は、子育て家庭がより安心して生活できる環境を整えることに役立ちます。
また、2024年10月に開始された児童手当の拡充などを含めた「子ども・子育て支援金制度」が2029年までに段階的に施行されていく予定です。これは少子化対策や子育て世帯への支援の必要性の高まりを受け、児童手当の拡充や妊娠時の支援給付として充てられます。
子育て支援で受けられる主なサポート内容
子育て支援制度では、以下のような具体的なサポートを受けることができます。
1. 経済的支援
児童手当:0歳から18歳まで、育児費用を支援するために2か月に1回、一定額が支給されます。
出産育児一時金:健康保険や国民健康保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に支給される公的制度です。通常、1児につき50万円が支給されます。
妊婦健診助成:妊娠中の妊婦健診費用を自治体が一部助成する制度です。本来、妊婦健診は保険適用外であるため、妊娠中に必要な健康チェックを受ける際の費用は通常自己負担となります。(自治体によって、助成の有無や費用、申請方法は異なります。)
2. 保育サービスの負担軽減
保育料の無償化:3歳から5歳の子どもは、支援新制度対象の幼稚園や保育所、認定こども園を利用した場合、保育料が無料になります。
一時保育サービス:急な用事や体調不良など休息を取りたい時に認可保育所等の施設で提供しているお子さまを短期的に預かるサービスのことです。利用料金が低額で気軽に利用できるのが魅力です。
東京都ベビーシッター利用支援事業:事業を実施する自治体の住民であれば、無料でベビーシッターを利用することができる制度です。
3. 医療・健康面の支援
母子健康手帳:妊娠が確定した際に、届出を提出することで自治体の窓口で無料でもらえます。
子どもの医療費助成:通常は、0歳から中学卒業までや高校卒業までを対象に、病院での診療費、薬代、入院費など、健康保険適用分の医療費の自己負担額を助成するものです。自治体によって対象年齢が異なります。
予防接種:子どもの病気予防のため、国が推奨する定期接種が無料で提供されています。
4. 相談・情報提供
子育て相談窓口:子育てに関する悩みを自治体の職員や専門機関へ無料相談することができます。
子育て支援センター:子どもを持つママ同士の交流を深める場です。子育てに関する情報交換をしたり、相談したりできるでしょう。
ファミリーサポート:子育てを手助けしてほしい人と、手助けをしたい人をつなぐ地域の子育て支援サービスです。多くは自治体の運営で、子どもの送迎や一時預かりなどを有償で提供しています。
主な支援制度についてご紹介しました。自治体によって提供しているサービスや内容が異なります。そのため、「自治体名 子育て支援」、「自治体名 制度の名前」など調べる時はお住まいの自治体や市役所名を入れて検索してみましょう。
ライフステージに合わせて使える制度
子育て支援と検索すると難しい制度が多くて、どれに申し込めばいいか分からないといったことも多いはず。
次はライフステージごとに一般的に利用可能な支援制度を紹介していきます。各制度の注意事項としては、ほとんどが自治体への申請が必要なことです。
| ライフステージ | 制度名 | 詳細説明 |
|---|---|---|
| 妊娠期 | 妊婦健診費助成 | 妊娠中の定期健診費用の一部を自治体が助成。里帰り出産に利用できる場合も。 |
| 母子健康手帳の交付 | 妊娠が確認された後に市区町村窓口で交付される。 | |
| 出産手当金 | 健康保険加入者が出産で休業中の所得を補償する手当。給与の約3分の2を補助する。 | |
| 出産育児一時金 | 健康保険加入者が出産時に、一児につき原則50万円が支給される。 | |
| 妊婦のための支援給付 | 妊婦のための支援給付金は経済的負担を軽減する補助金で、妊婦給付認定後に5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人につき5万円の2回支給される。 | |
| 国民年金保険料の免除 | 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度。 | |
| 妊娠高血圧症候群等の助成について | 妊娠高血圧症候群等で入院治療が必要な妊婦の自己負担医療費を助成する制度。 | |
| 出産費用の助成(入院助産) | 経済的理由や社会的困難で出産に支障がある妊婦を対象に、助産施設での入院出産費用を公費で助成する制度。 | |
| 新生児期(0歳) | 乳幼児医療費助成 | 乳幼児の通院・入院での自己負担分を自治体が助成。 |
| 定期予防接種 | 定期予防接種(予防接種法に基づく予防接種)は無料、任意予防接種は有料。 | |
| 乳幼児期(1歳~6歳未満) | 保育料無償化 | 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもたちの保育料が無料。また、認可施設に通う(非課税世帯)の0~2歳も無償。 |
| 保育料の補助制度 | 認可外保育施設の場合は3歳から5歳、(非課税世帯の)0~2歳には月額で保育料の補助がされる。 | |
| 児童手当 | 子育て支援の一環として、家庭の生活安定や児童の健やかな成長を目的に、0歳から高校生まで養育する保護者に支給される給付金。 | |
| 乳幼児健診 | 自治体により無料で受診でき、発育と発達の状況を確認するための健康診査。 ※対象年齢は自治体により異なる。 | |
| 一時保育利用料の補助 | 一時保育利用時の料金の一部を補助。地域によって条件が異なる。 | |
| 乳幼児歯科検診 | 乳幼児期の定期検診が無料もしくは2~3割負担で受診できる。自治体により対象年齢期間や負担額が異なる。 | |
| 小学校期(6歳~12歳) | 子ども医療費助成 | 乳幼児期が過ぎ、小中学生対象の医療証で医療費の助成を受けられる。※通院・入院を問わず、保険診療が対象の場合が多い。 |
| 学童保育料助成 | 保護者の就労・疾病等の理由により放課後の学童保育の料金を一部助成。※対象者は自治体により異なる。 | |
| 中学校期以上(12歳~18歳) | 子どもの学校給食費補助 | 経済的支援が必要な家庭への学校給食費を補助。所得制限がある自治体や事後申請のみの自治体もある。 |
| 高校生向け医療費助成 | 小中学生対象から高校生相当年齢まで医療証で医療費の自己負担額を助成する制度。 | |
| 住み替え家賃助成 | アパートに住んでいる18歳未満の子どもを養育している方で、住まいから転居が必要な場合に家賃の一部を助成。 | |
| 特定期間なし(子どもが0歳~15歳以下) | 子育てファミリー世帯への家賃助成 | 民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成し、負担軽減をすることで定住を目指す制度。※自治体により条件が異なる。 |
ライフステージに合わせて申請できる支援金や助成について説明しました。「知らなかった」、「申請期限が切れてしまっていた」とならないよう、対象の支援については確認して、必要な申請手続きを完了させるようにしましょう。
まとめ
子育て支援制度は、家庭の負担を軽減するための心強いサポートです。ただし、これらの制度を利用するには自治体への申請や手続きが必要です。対象の制度を逃さないように、妊娠中から自治体へ問い合わせたり、Webサイトで実施しているか確認したりすることをおすすめします。
しっかりと制度を活用して、育児生活をより豊かで楽しいものにしていきましょう。
※子育て支援制度は、法改正などにより内容が変更される場合や、自治体によって詳細が異なる場合があります。最新の情報や、お住まいの自治体で利用できる制度の詳細は、お住まいの自治体の窓口やウェブサイトをご確認ください。