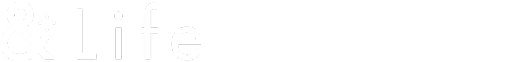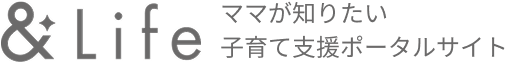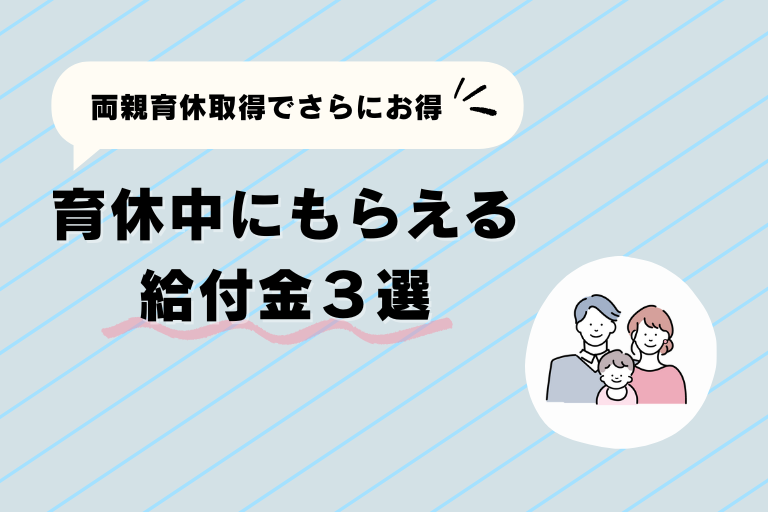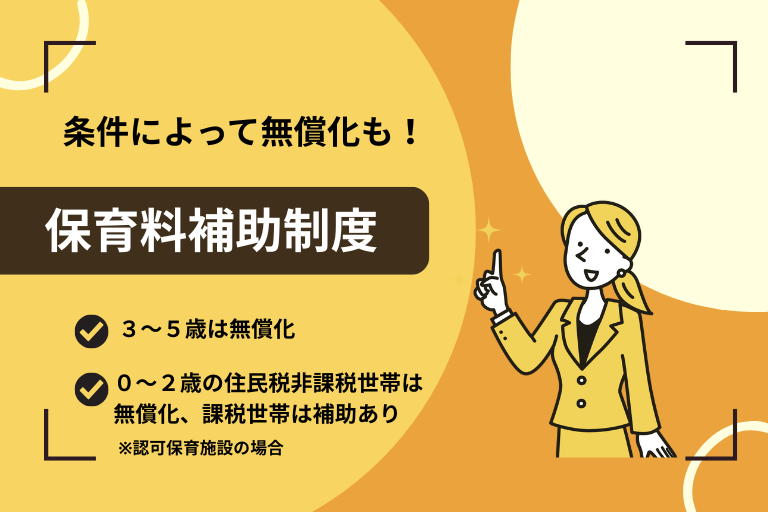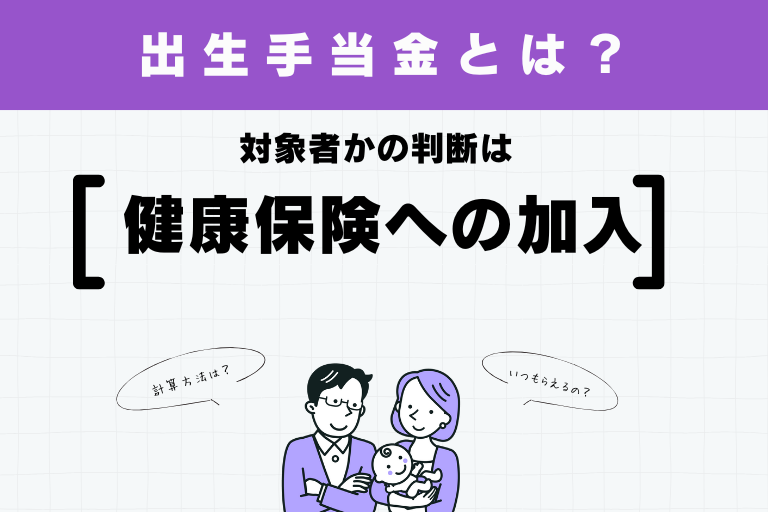初めての育児は、喜びとともにさまざまな不安もつきもの。特に、仕事との両立やお金のことに悩む方も多いのではないでしょうか。
そんな中、育児休業中の大きな支えとなるのが「育児休業給付金」、「出生時育児休業給付金(通称:産後パパ育休)」、そして2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」です。これらの制度を活用することで、家計への不安を和らげながら、大切な育児の時間を過ごすことができます。
目次
育児休業中にもらえる3つの給付金とは?
育児休業中に受給できる主な給付金は、以下の3つです。
1.育児休業給付金
2.出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)
3.出生後休業支援給付金
【3つの給付金の違い】
| 給付金の種類 | 育児休業給付金 | 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | 出生後休業支援給付金 |
| 対象者 | 父母どちらも対象(同時取得も可能) | 主に父親(母親も取得可) | 父母どちらも対象(要件あり) |
| 取得期間 | 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可、2回まで分割可) | 出生後8週間以内のうち最大4週間(分割可) | 出生後8週間以内に、対象要件を満たした最大28日間 |
| 支給率 | 休業開始から180日目まで:賃金日額の67%、それ以降:賃金日額の50% | 賃金日額の67% | 賃金日額の13% |
| 申請方法 | 勤務先を通じて申請 | 勤務先を通じて申請 | 勤務先を通じて他2つの給付金と合わせて申請可能 |
1.育児休業給付金の詳細
どんな制度?
雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した際に、一定の条件を満たせば賃金の一部が支給される制度です。子どもが1歳の誕生日の前日まで(条件を満たせば最長2歳まで)受け取れます。
支給額の目安
- 育休開始から180日目まで:賃金日額の67%
- 181日目以降:賃金日額の50%
たとえば月収30万円の方であれば…
- 180日目まで:約20万円/月
- 181日目以降:約15万円/月
支給期間
- 原則:子が1歳になるまで(2回まで分割して取得可能)
- 条件により最長2歳まで延長可能(保育所に入れない場合など)
受給資格
- 雇用保険の被保険者
- 育休開始前2年間に「11日以上働いた月」が12か月以上ある
- 育児休業を取得している
- 休業中の就労が月10日以内、または80時間以内
申請方法・期限
- 会社を通じてハローワークに申請
- 必要書類:育児休業給付受給資格確認票・支給申請書など
- 申請期限:育児休業開始日から2か月以内
2.出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の詳細
どんな制度?
父親が子どもの出生直後から育児に参加しやすくなるよう、出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できる制度。母親も取得可能です。
支給額
- 賃金日額の67%
支給期間
- 出生後8週間以内のうち、最大28日間(分割取得可)
受給資格
- 雇用保険の被保険者
- 育児休業を取得している
- 育休前2年間に「11日以上働いた月」が12か月以上あること
- 休業期間中の就業が月10日以内、または80時間以内
申請方法・期限
- 勤務先を通じて申請
- 必要書類は育児休業給付金と同様
- 申請期限:育児休業開始日から2か月以内
3.出生後休業支援給付金の詳細
どんな制度?
両親がともに子の出生直後から一定期間育児休業を取得した場合、または配偶者が育児休業を取得できない等の要件を満たした場合に支給される給付金です。家庭環境にかかわらず育児休業取得を促進することを目的に、2025年4月より新たに創設されました。
支給額の目安
休業開始前の賃金の13%相当
支給期間
出生後8週間以内に、下記のいずれかの条件を満たす場合、最大28日間支給。
- 両親それぞれが14日以上(連続または分割)の育児休業を取得した場合
- 配偶者が育児休業を取得できない等の要件を満たした場合
受給資格
- 雇用保険の被保険者であること
- 上記の支給期間の条件を満たすこと
- 育児休業給付金または出生時育児休業給付金の受給資格を満たしていること
申請方法・期限
会社を通じて申請(育児休業給付、出生時育児休業給付と同時申請可能)
補足|3つの給付金はそれぞれ条件が異なります!
育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金は、それぞれ受給条件や支給期間が異なります。
出生後休業支援給付金は、他の2つの給付金に上乗せして支給されます。
どの給付金が受け取れるかは、育休の取得期間やタイミング、両親の取得状況などによって変わるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
まとめ|制度を正しく知って、安心して育児に専念しよう
育児休業給付金、出生時育児休業給付金、そして出生後休業支援給付金は、育児と仕事の両立を後押ししてくれる大切な制度です。制度を正しく理解し、早めに準備することで、経済的な不安を軽減しながら子どもとのかけがえのない時間を過ごすことができます。
詳細な情報や最新の制度改正については、厚生労働省のウェブサイトや、お住まいの自治体の窓口などで確認しましょう。