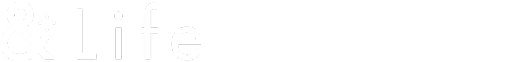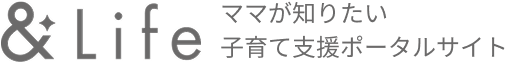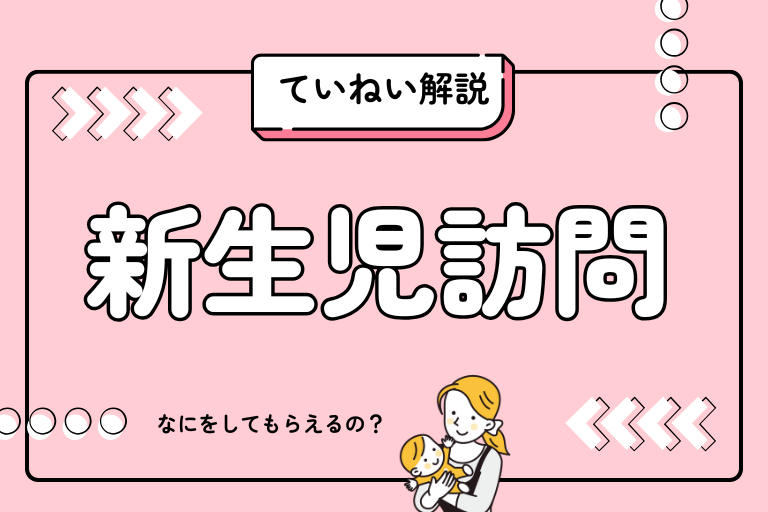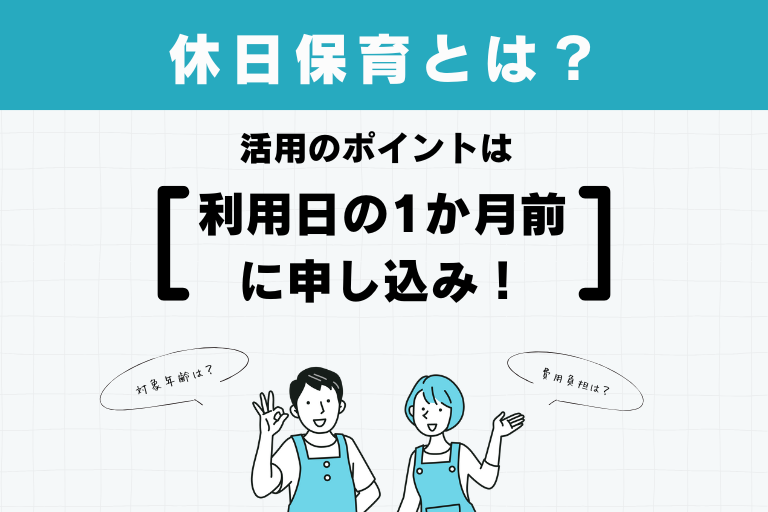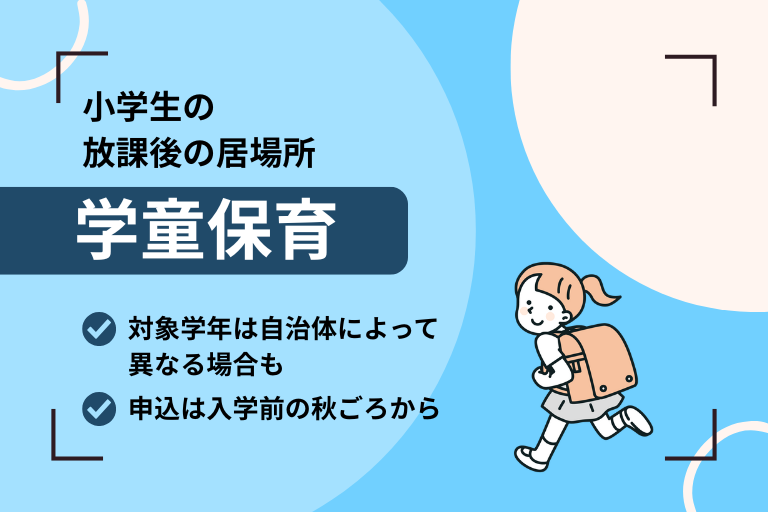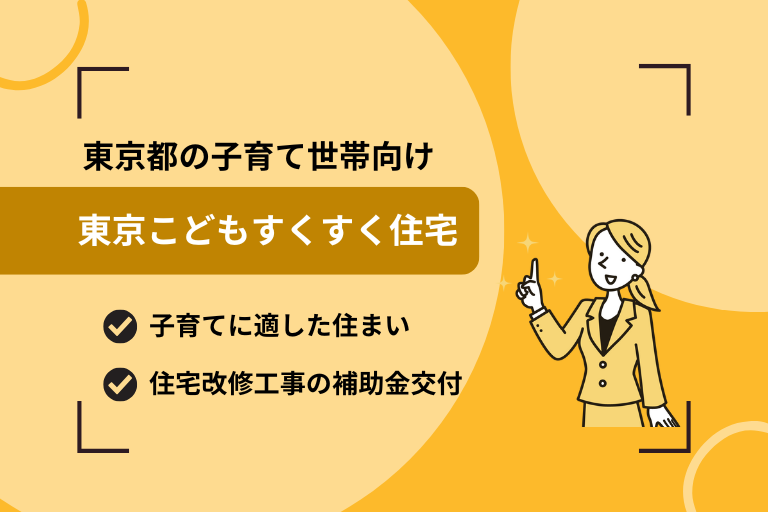子育てがスタートすると、うれしさや幸せ以上に、新米ママやパパには不安や疑問がたくさん押し寄せてきます。特に産後間もない時期は、ママ自身の体調も完全に戻らない中で、赤ちゃんのお世話に奮闘する日々。そんな大変な時期に、育児をプロがサポートしてくれる制度があるのをご存じでしょうか?それが「新生児訪問」です。
ここでは、新生児訪問の内容やメリット、受ける際の準備などについて詳しく解説していきます。
新生児訪問とは?制度の仕組みを知ろう
新生児訪問は、赤ちゃんが生後4か月以内(自治体によって対象期間が異なる場合あり)の家庭を対象に、保健師や助産師が自宅を訪問して親と子の健康状態を確認し、育児をサポートする制度です。この制度は厚生労働省が母子保健法に基づいて全国の自治体に実施を推進しているため、ほとんどの地域において無料で利用可能です。
訪問については、自治体から郵送による通知や電話にて案内されることが一般的です。「自宅に保健師が来る」という安心感が得られるため、特に産後の不安が多い時期には心強いサポートとなります。
新生児訪問のメリット
新生児訪問の最大のメリットは、病院に行かなくても専門職によるサポートを受けられることです。同時に、以下のような点で心身ともに安心感を得ることができます。
- 赤ちゃんの健康チェック
自宅で赤ちゃんの体重や身長を測定し、成長が順調かどうかを確認します。また、肌の状態やお腹の張りなどもチェックしてもらえるため、早期に気になる点を発見することが可能です。
- ママの体調と心理的サポート
産後間もないママの体調や心の状態も確認してくれます。産後うつの予防や心理的な不安解消への配慮が行われるため、産後の負担が軽減される大切な機会です。
- 地域の育児支援情報提供
地域の子育て支援サービスについての情報を教えてもらえます。母子手帳を活用した制度や育児教室などの情報を聞き、自分の家庭が利用できる具体的な支援を知ることができます。
新生児訪問では何をしてくれるの?

- 赤ちゃんの健康や育児相談
授乳やおむつ替え、赤ちゃんが泣き止まないときの対処法など、育児に関する日常的な悩みを解消するためのアドバイスが得られます。
- 家庭環境へのアドバイス
部屋の湿度や温度など、赤ちゃんが快適に過ごせる生活環境作りについて具体的なアドバイスをしてもらえます。季節や気候に応じた提案も受けられるため、すぐに生活へと取り入れられます。
新生児訪問を受ける流れ
- 案内を受け取る
自治体へ「出生通知票」を提出後、郵送や電話にて実施時期や訪問内容の案内があります。
- 日程の調整
担当者と連絡を取り、訪問日時を調整します。オンラインや電話で手続きする場合が多いです。
- 訪問前の準備
特別な準備は不要です。部屋が散らかっていても問題ありませんし、お茶を出す必要もありません。保健師の訪問は育児の支援が目的なので、自然な状態で迎えましょう。
訪問時に聞いておくべきことは?
訪問の時間は限られているため、産後の不安を解消するための質問項目を事前に整理しておくことがおすすめです。以下は質問例です。
- 赤ちゃんの授乳間隔やミルクの量は合っていますか?
- 赤ちゃんが泣いている理由がわかりません。どう見分ければよいですか?
- 室温や服を着せる枚数はどのくらいが赤ちゃんに適していますか?
- 赤ちゃんの肌が荒れやすいのですが、スキンケアの方法はありますか?
- 睡眠をとる時間がなくてつらいです。この状態をどうすればいいですか?
- 体調がまだ戻らないのですが、この症状は普通ですか?
- 自治体で提供されている子育て支援はどのようなものがありますか?
お母さんと赤ちゃんの状況や状態に合わせて、親身になって回答してもらえるでしょう。紙とペン、アプリのメモ機能など、忘れずに用意しておきましょう。メモが難しい場合は、ボイスメモなどのアプリ機能の活用もおすすめです。
全国共通の制度でも地域ごとに特色あり
新生児訪問は全国共通の制度として運用されていますが、自治体によって細かい実施内容は異なる場合があります。例えば、赤ちゃんが生後4か月まで対応している地域や、4か月以降もフォローアップを実施している自治体もあります。気になる場合は、通知が届いた際に自治体の担当窓口に確認してみてください。
まとめ
新生児訪問は、行政が提供する安心の仕組みであり、新米家庭に寄り添う重要なサポートです。赤ちゃんと親の健康を確認しつつ、育児の悩みを解決する貴重な機会です。
事前に疑問や悩みをメモしておき、質問を整理することで、専門職から的確なアドバイスを得ることができます。初めての育児を一人で抱え込まず、ぜひ行政サービスを活用し、安心の子育て環境を整えましょう。
※新生児訪問は自治体によって細かな内容や手続きが異なる場合があります。詳細については、お住まいの自治体へお問い合わせください。