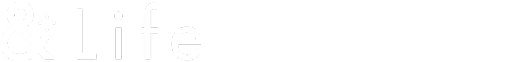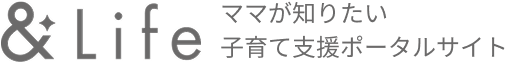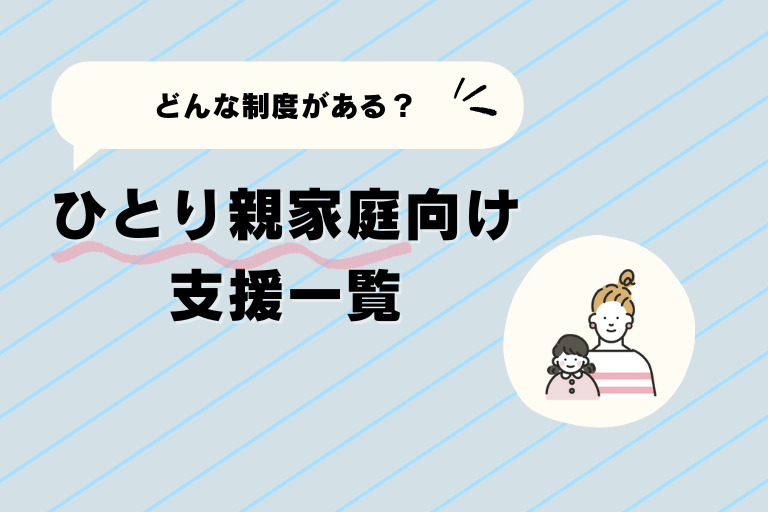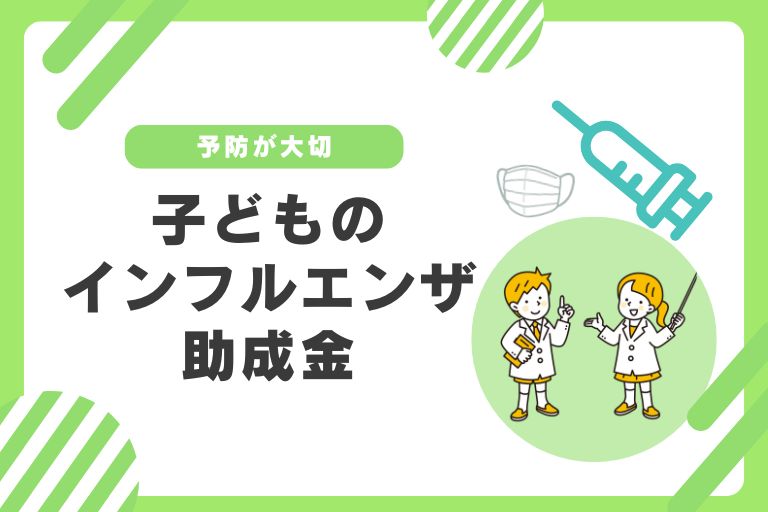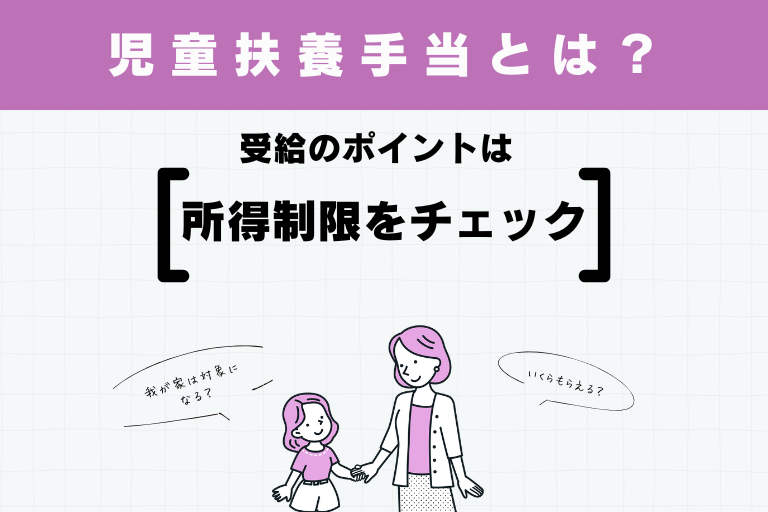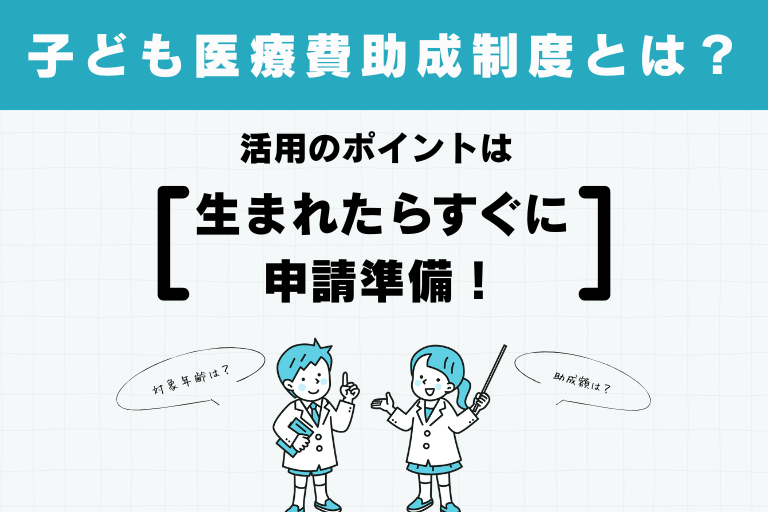現代社会では、3組に1組の夫婦が離婚を選択するといわれています。そのような中、ひとり親家庭は、仕事と子育てを両立し、経済的な厳しさに直面することが少なくありません。児童扶養手当は大切な支援ですが、それだけでは不十分と感じる方も。本記事では、ひとり親家庭を多角的に支える多様な公的支援制度を具体的に解説します。
目次
児童扶養手当以外の主要な支援制度
ひとり親世帯向けの支援制度は、「児童扶養手当」以外にも、さまざまな制度があります。児童扶養手当については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ここからは、児童扶養手当以外の、国や地方自治体が「子育て・生活支援」、「就業支援」、「養育費確保等支援」、「経済的支援」の4本柱でひとり親家庭をサポートしている具体的な支援制度を見ていきましょう。
医療費に関する支援
ひとり親家庭には、医療費の自己負担分を軽減する制度があります。これは「ひとり親家庭等医療費助成制度」と呼ばれ、自治体によって名称や内容が異なりますが、医療費の自己負担分の一部または全額を助成するものです。
例えば、受給対象の子どもが18歳になる年度末(障害がある場合は20歳未満)まで、通院・入院費の一部が助成されるといった内容です。
児童扶養手当を受給している場合、医療費助成の対象となることが多いですが、自治体によって条件が異なります。詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
住まいに関する支援
住居に関する支援も、ひとり親家庭には大きな助けとなります。
- 公営住宅の優先入居:多くの自治体では、ひとり親家庭が公営住宅に入居する際に、一般世帯よりも優遇される制度を設けています。家賃が比較的安価なため、生活費の大きな負担軽減につながります。
- 住宅手当・家賃補助:一部の自治体では、特定の条件を満たすひとり親家庭に対し、家賃の一部を補助する制度や、転居費用を支援する制度を設けている場合があります。
- 母子生活支援施設:DV被害や貧困などにより、緊急性が高く住居を失う恐れがある場合に、子どもと一緒に一時的に入所できる施設です。生活相談や自立支援も行われます。
就労・自立を支える支援
ひとり親家庭が経済的に自立できるよう、就労を促進し、生活を安定させるためのさまざまな支援策が用意されています。
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金:
これは、ひとり親家庭の経済的自立と子どもの福祉増進を図るための貸付制度です。資金の種類は多岐にわたり、事業の開始資金、子どもの修学資金、生活資金、医療介護資金、住宅資金など、目的に応じた貸付を低利子または無利子で受けることができます。
- 自立支援教育訓練給付金:
ひとり親が、就職に有利な資格取得やスキルアップを目指すために、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講する際にかかる費用の一部を助成する制度です。看護師、介護福祉士、IT関連の資格など、多岐にわたる講座が対象となります。
- 高等職業訓練促進給付金:
上記の自立支援教育訓練給付金と併せて利用できる制度で、教育訓練受講期間中の生活費の負担を軽減するために支給されます。資格取得のための学習期間中に収入が減少しても、安心して学習に専念できるよう支えるものです。
- ハローワーク等での就労支援:
ハローワークには、ひとり親家庭専門の相談窓口が設置されている場合があり、就職に関する相談、求人情報の提供、履歴書作成支援など、きめ細やかなサポートを受けることができます。
教育に関する支援
子どもの教育費は、ひとり親家庭にとって大きな負担となりがちです。国や自治体は、学費の負担を軽減するための制度を複数用意しています。
- 就学援助制度:
経済的に困難な状況にある家庭(ひとり親家庭も含む)に対し、義務教育にかかる費用(給食費、学用品費、修学旅行費、校外活動費など)の一部または全額を補助する制度です。市区町村の教育委員会が窓口となります。
- 高校授業料無償化・就学支援金:
公立高校の授業料は無償化されており、私立高校に通う場合でも、世帯所得に応じて授業料を支援する「高等学校等就学支援金制度」があります。この制度により、高校教育の機会均等が図られています。
- 高等教育の修学支援新制度:
大学、短期大学、専門学校など高等教育機関への進学を支援するもので、授業料や入学金の減免、給付型奨学金の支給が行われます。所得状況などに基づき支援を受けられ、ひとり親家庭の場合、所得要件を満たしやすく支援対象となる可能性があります。
- 各種奨学金制度:
国(日本学生支援機構)や地方自治体、民間団体などが提供するさまざまな奨学金制度があります。貸与型(返還が必要)と給付型(返還不要)があり、ひとり親家庭向けの優遇措置が設けられている場合もあります。
税金・国民健康保険料に関する優遇措置
税金や社会保険料においても、ひとり親家庭を対象とした優遇措置があります。
- ひとり親控除・寡婦控除:
所得税や住民税の計算において、特定の条件を満たすひとり親に対し、所得から一定額を控除する制度です。これにより、課税される所得額が減り、税負担が軽減されます。未婚のひとり親も対象となる「ひとり親控除」と、夫と死別・離婚後に再婚していない「寡婦控除」があり、それぞれ適用条件が異なります。
- 国民健康保険料・国民年金保険料の減免制度:
所得が低い場合や、災害などの特別な事情がある場合、国民健康保険料や国民年金保険料が減額または免除される制度があります。これにより、生活費の負担を軽減し、セーフティーネットの維持を助けます。
その他の支援
上記以外にも、ひとり親家庭を支援するためのさまざまな制度やサービスがあります。
- 生活保護制度:あらゆる努力をしてもなお生活に困窮する場合の、最後のセーフティーネットとして機能します。
- 自治体独自の取り組み:地域によっては、子育て支援パスポートの配布、無料相談会、食料支援、子ども食堂の運営など、独自の支援サービスを提供している場合があります。
賢く活用するために:情報収集と相談窓口
ひとり親家庭向けの支援制度は数多く、住んでいる地域や個人の状況によって利用できるものが異なります。これらの制度を最大限に活用するために、以下の点を心がけましょう。
- 積極的な情報収集:制度は法律の改正や年度が新しくなると、更新される可能性があります。こども家庭庁のウェブサイトや各自治体のウェブサイトなどで最新情報を確認しましょう。
- 条件の確認:ほとんどの制度には所得制限や特定の条件があります。ご自身の状況が当てはまるか、必ず詳細を確認してください。
- 専門機関への相談:一人で悩まず、積極的に相談することが、最適な支援を見つける第一歩です。
参考サイト例:こども家庭庁 あなたの支え、東京都福祉局 くらし応援ナビ
主な相談窓口は以下の通りです。
- 市区町村の窓口:お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課、福祉課など)へ。地域の制度に最も詳しく、具体的な手続きの案内も受けられます。
- ひとり親家庭等就業・自立支援センター:ひとり親家庭の就業や生活全般に関する専門的な相談ができます。
- 母子・父子自立支援員:各自治体に配置されており、生活や自立に関する計画策定のサポートをしてくれます。
まとめ
上記で紹介したように、ひとり親世帯向けの支援制度には児童扶養手当以外にも、経済、住まい、教育、就労、税金など、多くあります。一人で抱え込まず、積極的に情報を集め、お住まいの自治体や専門窓口に相談してください。利用できる支援を最大限に活用し、安心して子育てをしていきましょう。
※本記事は、2025年9月現在の情報に基づき作成しています。最新かつ詳細な情報は、こども家庭庁のウェブサイトやお住まいの自治体の窓口などでご確認ください。