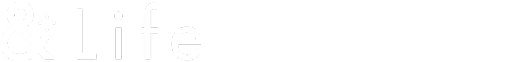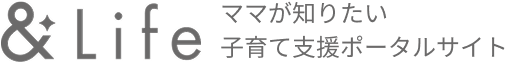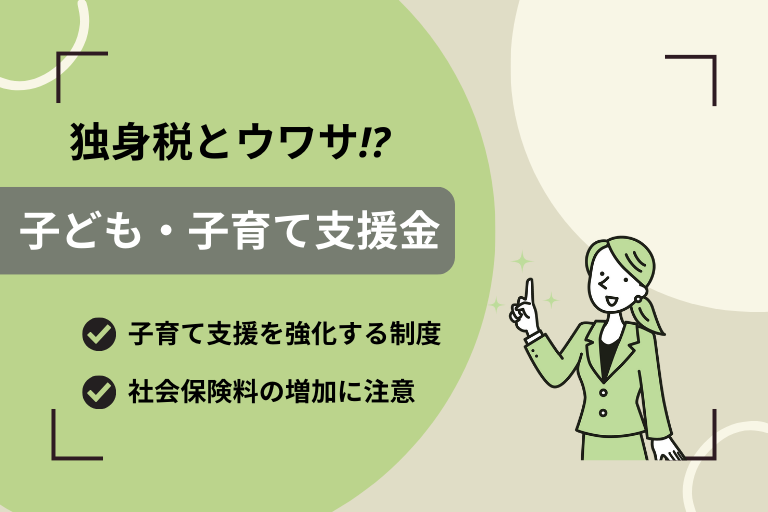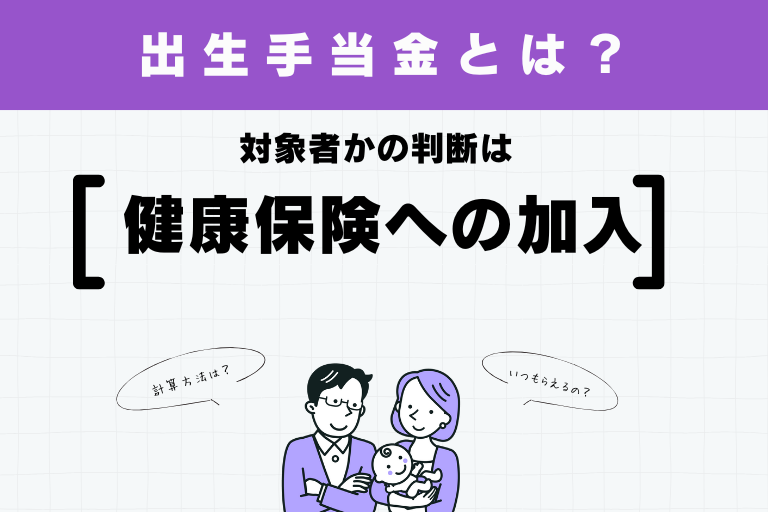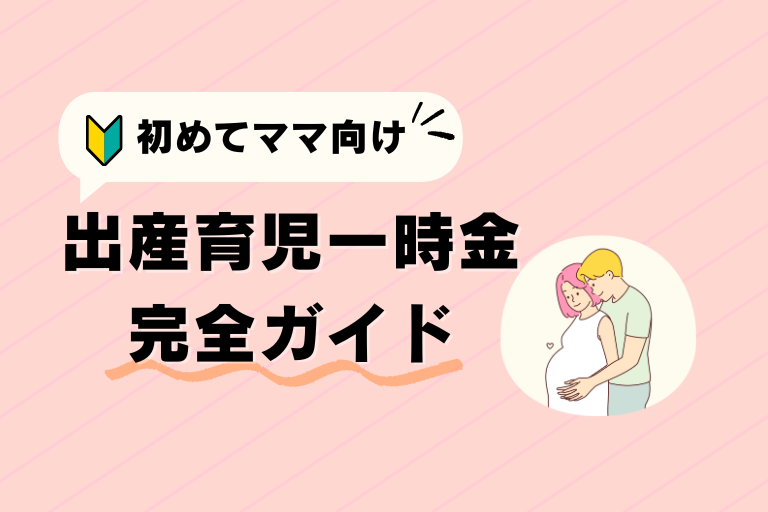日本では少子化が進み、子育て支援の拡充や質の向上は社会全体で取り組むことが必要です。そこで、子育て家庭を応援してくれる「子ども・子育て支援金制度」は、国や自治体が中心となり、教育費や保育費などの負担を医療保険料の財源を元に軽減する仕組みです。この記事では、具体的な制度内容や負担額をわかりやすくまとめました!
1. 子ども・子育て支援金とは?
「子ども・子育て支援金」は、子育て家庭に向けて国や自治体が提供する、子育て支援の強化を目的とした新しい経済的支援制度です。少子化が進む現代社会において、子どもの成長を見守る家庭の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整える目的で2026年4月から開始される予定です。
私たちがどんな影響を受けるかですが、「子ども・子育て支援金」の財源の確保として、公的医療保険に上乗せされます。つまり、2026年4月以降から社会保険料が増加することになります。これは、所得に応じて金額は変化しますが、社会人からご高齢の方、事業主の方を含む全世代・全経済主体から拠出されることになります。
2. どんな支援内容なの?
具体的な施策としては、「こども未来戦略」に基づきプランがとりまとめられています。主な支援金を利用した事業は下記です。
児童手当の拡充:所得制限を撤廃し、対象年齢の引き上げや児童手当の金額増加など、さらに利用しやすい支援となるよう、2024年10月から制度改正が行われています。
妊婦のための支援給付:妊娠・出産時に合わせて10万円の経済支援がもらえます。
乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月あたり10時間を目途に、柔軟な通園をできるよう支援する制度です。
出生後休業支援給付:出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合などに、休業開始前の賃金の13%相当額が追加で支給されます。この給付金は、育児休業給付金と併せて支給されることで、休業期間中の手取りが賃金の10割に近づくよう設計されています。
育児時短就業給付:2歳未満の子がいる場合の時短勤務中に、支払われた賃金の10%を支給する制度です。
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業などの国民年金第1号被保険者の子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料を免除する制度です。
3. 負担額はいくら?
先述したように子ども・子育て支援金は、公的な医療保険料と合わせ徴収され、社会全体で子育て世帯を支えていく仕組みです。すでにこども家庭庁では、2026年から2028年までの見込み額を公開しています。
| 年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | ||||
| 加入医療保険 | 加入者1人当たり | 被保険者1人当たり | 加入者1人当たり | 被保険者1人当たり | 加入者1人当たり | 被保険者1人当たり | |
| 被用者保険(会社員、公務員) | 被用者保険 | 300円 | 450円 | 400円 | 600円 | 500円 | 800円 |
| 協会けんぽ | 250円 | 400円 | 350円 | 550円 | 450円 | 700円 | |
| 健保組合 | 300円 | 500円 | 400円 | 700円 | 500円 | 850円 | |
| 共済組合 | 350円 | 550円 | 450円 | 750円 | 600円 | 950円 | |
| 国民健康保険 | 250円 | 350円 | 300円 | 450円 | 400円 | 600円 | |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 | ||||
※国民健康保険は1世帯あたりの金額です。
3年間で支払う費用の目安は、月額250円から450円のため、年間5,000円ほど社会保険料が上乗せされる見込みです。どの医療保険かによっても金額が異なるため、自分の金額を確認してみましょう。
子どもがいる方に注目してほしいのは「被保険者1人当たり」の金額です。扶養されている子どもなどの国民医療保険加入者は、保険料を支払いません。そのため、被保険者である方に負担がかかり、被保険者1人当たりでみると月額450円から950円の増加となっています。
国民健康保険および後期高齢者医療制度の対象者には、所得に応じた軽減措置がなされ、被保険者の支援金額に一定の限度を設けるとされています。さらに、国民健康保険は子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳になるまで子どもにかかる支援金については軽減する措置も検討されています。
また、年収別に応じて負担額が変動するとされています。こちらも社会保険料の月額と同様、2026年から2028年にかけて、徐々に負担額が増加する見込みです。ここでは、負担額が1番大きくなる2028年度を取り上げます。
【年収別支援金額の目安(月額)】
| 年収 | 会社員・公務員 | 自営業者(個人事業主、フリーランスなど) |
| 200万円 | 350円 | 250円 |
| 400万円 | 650円 | 550円 |
| 600万円 | 1,000円 | 800円 |
| 800万円 | 1,350円 | 1,100円 |
| 1,000万円 | 1,650円 | 未公表 |
4. 独身税と呼ばれる理由は?
制度が採択された際、一部のメディアやSNSでは「子ども子育て支援金」を「独身税」と呼称することがあり、話題となっていました。先述しているように、実際には「独身者にだけ課される税金」ではなく、公的な医療保険料と合わせて徴収され、国民全体から支援金が集められます。
支援内容は、子どもを持つご家庭への支援金として使われるため、独身の方や高齢者の方の中には、負担が増えるにもかかわらず「還元されない」と感じる方も一定数いるかもしれません。しかし、子育ては社会全体が直面している問題と位置づけされています。独身や子どもがいない人も含めて広く支援金を負担し、子どもがのびのびと暮らせる経済的、社会的な環境を整えていくことが重要です。
※こども・子育て支援金は2026年春に開始予定の新しい制度です。そのため、本記事で紹介した支援金額などは執筆時点(2025年8月)では検討段階のため、変更になる場合があります。最新情報はこども家庭庁公式サイト等でご確認ください。
まとめ
「子ども・子育て支援金」は、児童手当など、子育て家庭の負担を大幅に軽減する制度です。対象者は基本的にすべての国民ですが、特に支援を必要とする子育て家庭は軽減措置なども検討されています。子育ての毎日がもっと安心できるものになり、社会全体にプラスの影響となっていけばいいですね。
出典:
・こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について