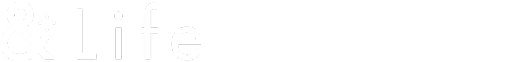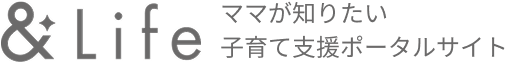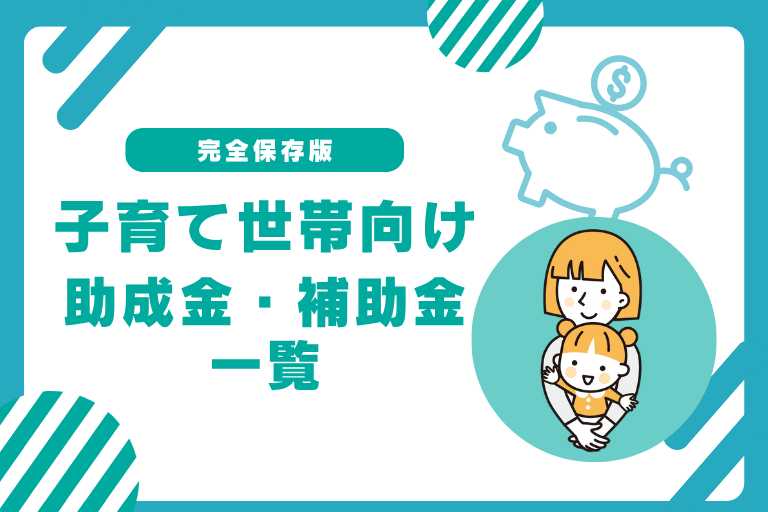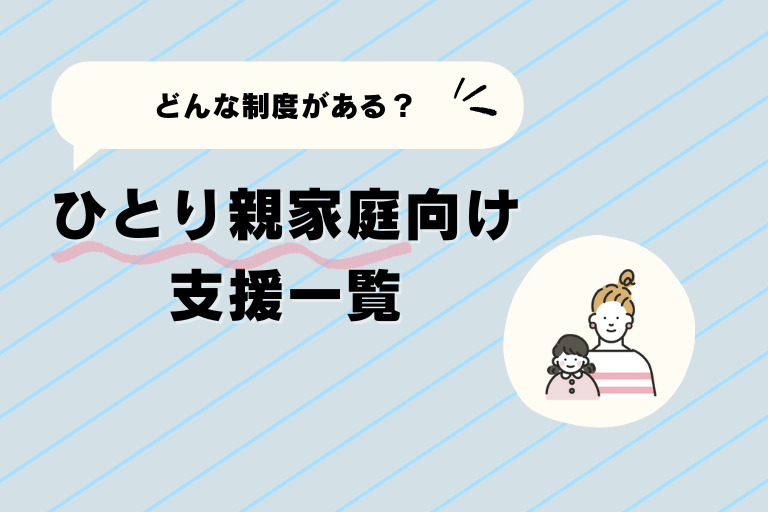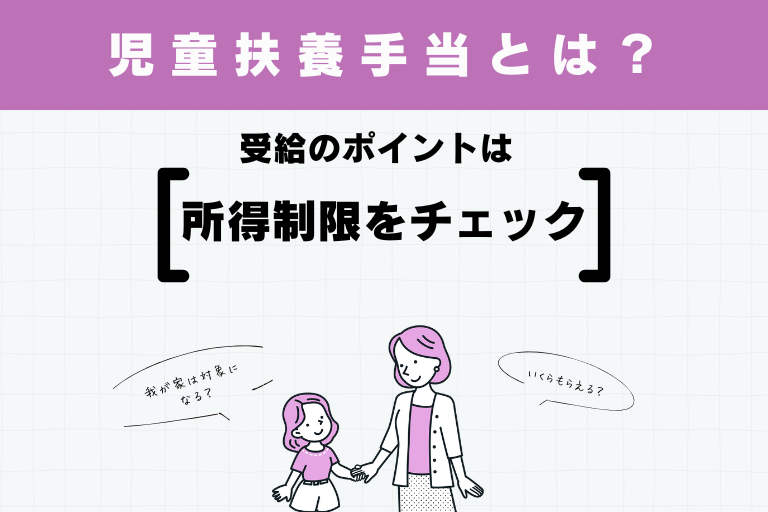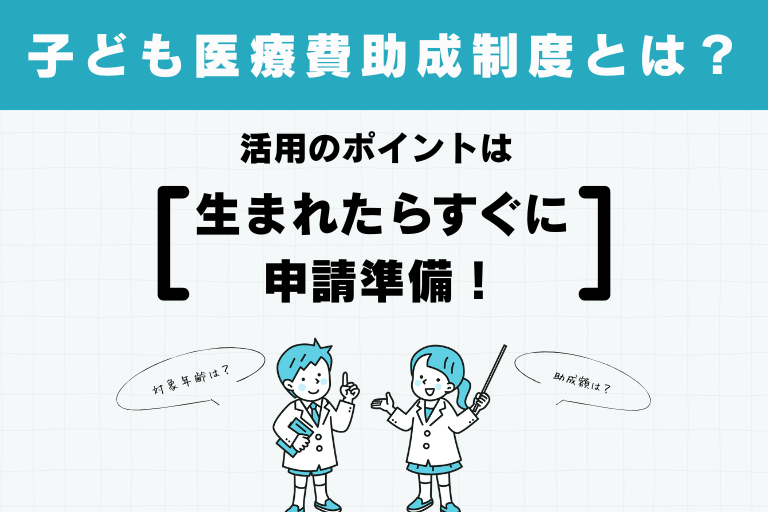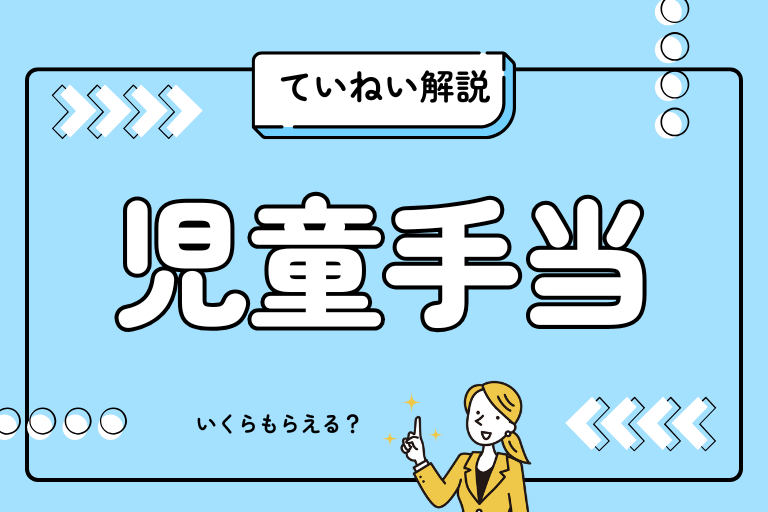子育てには、ミルク、おむつ、教育費など、想像以上にお金がかかります。将来に備えた貯蓄もしたいけれど、なかなか余裕がない…と悩む子育て世帯も多いのではないでしょうか? そんなご家庭を支えるため、国や自治体ではさまざまな補助金・助成金制度を用意しています。本コラムでは、利用できる主な制度の概要を分かりやすく解説。ぜひ、家計管理にお役立てください。
子育て補助金・助成金の全体像
子育て補助金・助成金は、大きく分けて出産関連、育児休業関連、保育・教育関連、医療費関連、住宅関連などに分類できます。また、支給主体も国、都道府県、市区町村とさまざまです。それぞれに受給資格や申請方法、所得制限の有無、その基準額が異なるため、注意が必要です。申請方法は、窓口申請、郵送申請、オンライン申請など、制度によって異なります。
主な子育て補助金・助成金
ここでは、代表的な子育て補助金・助成金をご紹介します。それぞれの内容については、今後公開予定の個別記事で詳しく解説しますので、そちらもぜひご覧ください。
出産関連
- 出産育児一時金: 出産にかかる費用として、原則50万円が支給されます(2023年4月1日以降の出産が対象)。双子以上の場合、子ども1人につき50万円が加算されます。医療機関によっては直接支払制度も利用可能です。
- 出産手当金: 会社員や公務員など、健康保険や共済組合に加入している本人が、出産に伴う休業を取得した場合、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
出産育児一時金の具体的な金額や申請方法は、こちらの記事をご覧ください。
出産手当金の対象者やもらえる金額は、こちらの記事をご覧ください。
育児休業関連
- 育児休業給付金: 雇用保険に加入している人が育児休業を取得した場合、最長1歳まで(条件により延長可)、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)が支給されます。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休): 出生後8週間以内に最大4週間(分割取得可)の育児休業を取得すると、賃金日額×休業日数×67%相当額が支給されます。雇用保険加入者である父母どちらでも取得可能ですが、父親の取得が推奨されています。両親共に育休取得などの一定の要件が必要です。
- 出生後休業支援給付金(2025年4月新設): 子の出生直後に夫婦共に育児休業を取得した場合に、給付金を上乗せする形で支給される制度です。
- 育児時短就業給付金(2025年4月新設): 2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている場合に支給される給付金です。
育児休業給付金など、育児休業中の給付金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
保育・教育関連
- 児童手当: 0歳から高校生年代まで、子どもの年齢に応じて支給される手当です。年齢や所得によって金額が変わります。
- 保育料の補助:認可保育園、認定こども園、幼稚園などの保育料は、3歳〜5歳児クラスは無償化、0歳〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が無償化、課税世帯は補助の対象となります。補助額は自治体や住民税額によって変わります。
- 認可外保育施設の補助: 認可外保育施設を利用する場合、「保育の必要性」の認定を受けることで、施設利用料の一部が補助されます。補助額や対象条件は自治体によって異なります。
- 高等学校等就学支援金制度: 公立高等学校の授業料を実質無償化、および、私立高等学校等に通う生徒の授業料負担を軽減するための支援金制度です。※年収約910万円未満の世帯が対象で、世帯所得に応じて支給額が変動します。
児童手当の給付額や申請方法など詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
保育料の補助・無償化についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
医療費関連
- 子どもの医療費助成制度: 子どもの医療費の自己負担額を軽減または全額助成する制度。対象年齢や助成内容は自治体によって大きく異なります。
住宅関連
- 子育てグリーン住宅支援事業: 子育て世帯等が新築住宅を取得する場合、省エネ性能に応じて補助金が交付される事業です。一定の省エネ改修や子育て対応改修等を行うリフォーム工事も補助対象となります。
その他
- ひとり親家庭等日常生活支援事業: ひとり親家庭等に対し、養育費の確保や就労、住宅などの支援があります。
- 多子世帯向け支援: 子どもが3人以上いる世帯に対し、保育料の軽減・減免、各種助成などがあります。
自治体独自の支援策
国が実施する制度以外にも、各都道府県や市区町村が独自に実施している子育て支援策があります。
例:
- 子育て応援クーポンの配布
- おむつやミルクの無料提供
- タクシー券・ベビーシッター利用助成など
お住まいの自治体のホームページ等で確認してみましょう。里帰り出産などで複数の自治体に関わる場合は、それぞれの自治体の制度を丁寧に確認することが大切です。
まとめ
子育てには何かと費用がかさみ、家計への負担は大きくなりがちです。しかし、ご紹介したように、子育て世帯を支援するためのさまざまな補助金・助成金制度が用意されています。これらの制度を積極的に活用することで、家計の負担を軽減し、ゆとりある子育てを実現できるはずです。
申請手続きは煩雑に感じることもあるかもしれませんが、得られるメリットは大きいです。最新の情報を確認し、ぜひ活用してみてください。
※制度の内容は変更される可能性がありますので、必ずお住まいの自治体による公式の情報をご確認ください。